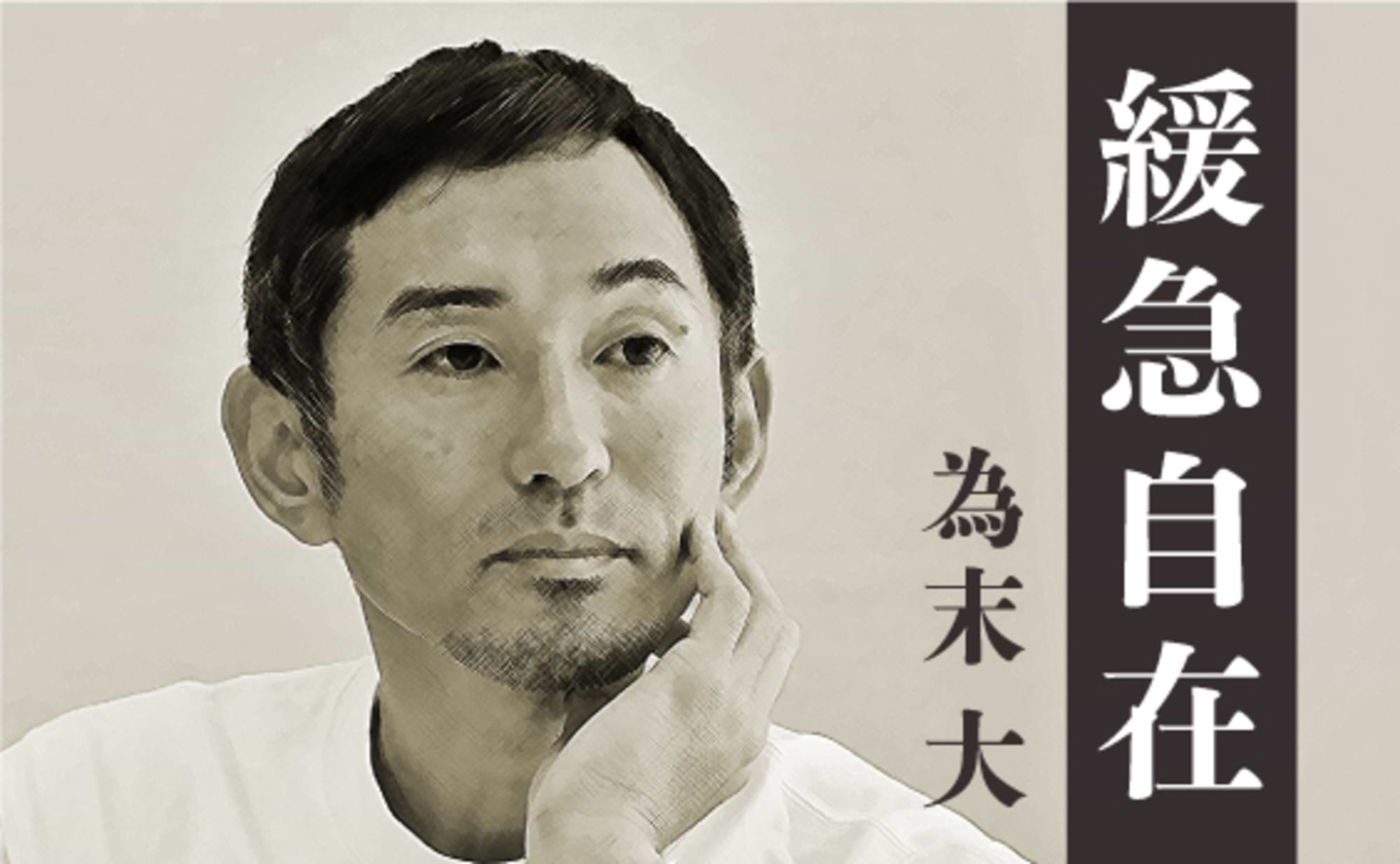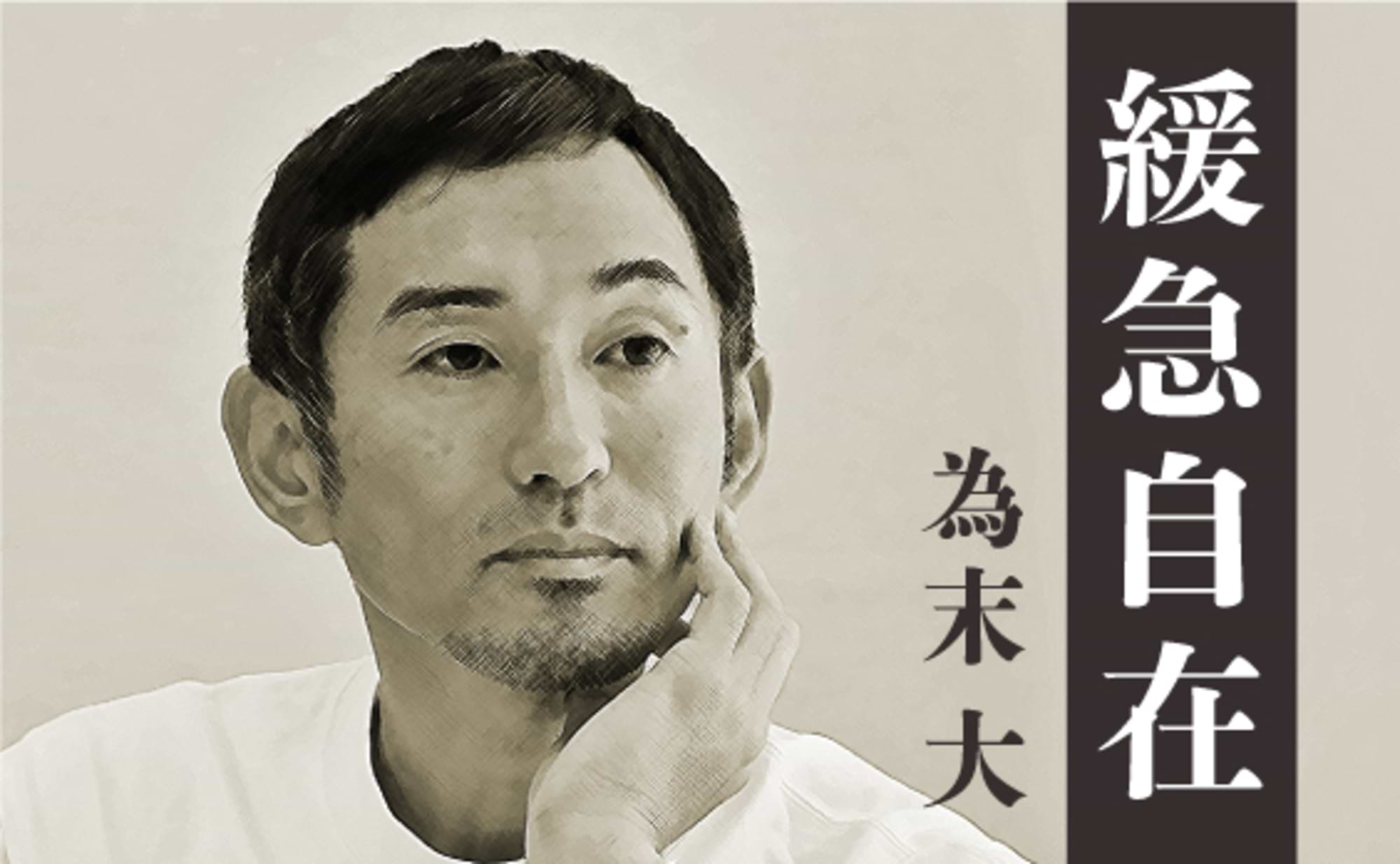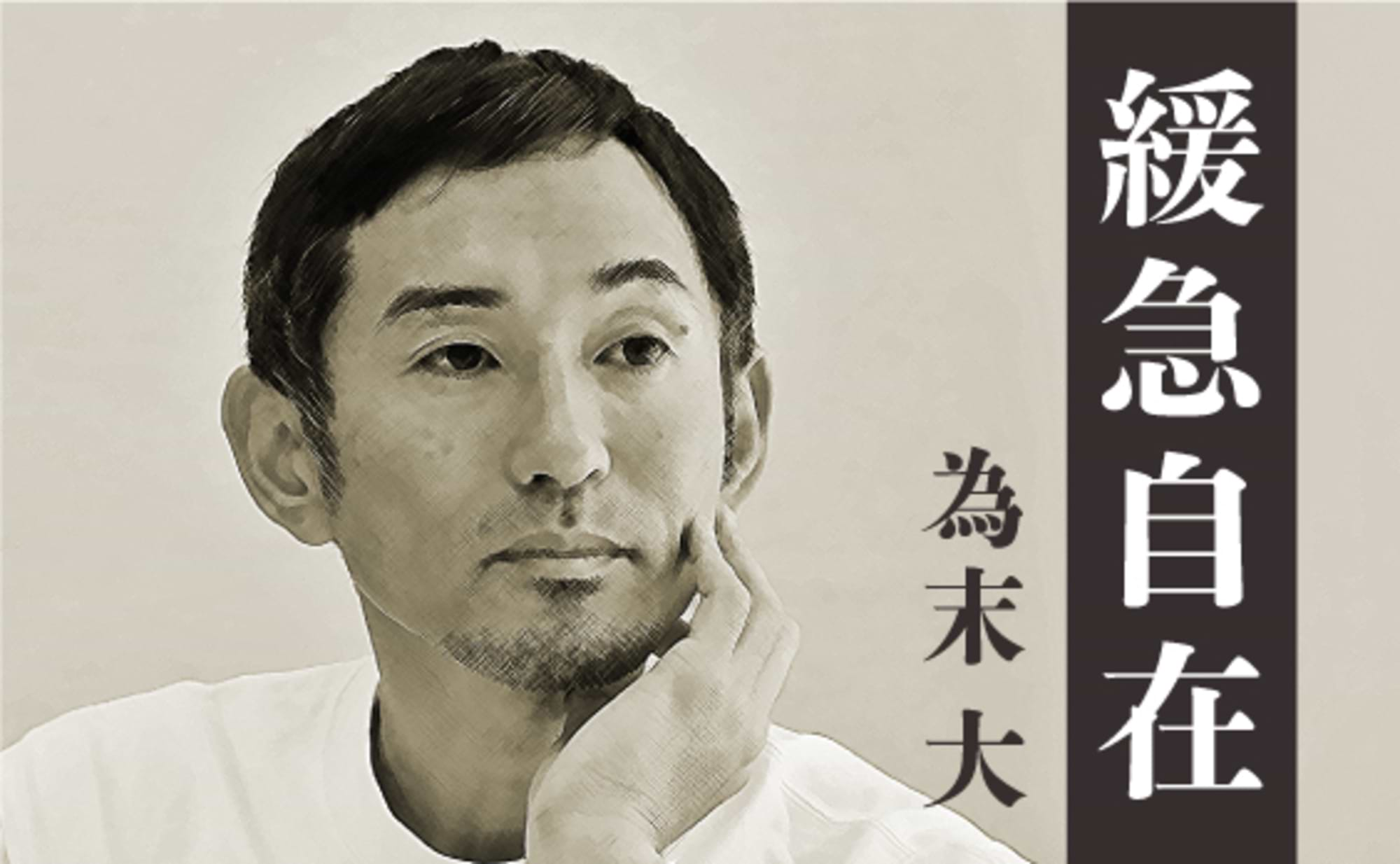為末大さんに「いま、気になっていること」について、フリーに語っていただく連載インタビューコラム。唯一、設定したテーマは「自律とは何か、寛容さとは何か」。謎の「聞き手」からのムチャ振りに為末さんが、あれこれ「気になること」を語ってくれます。さてさて。今回は、どんな話が飛び出すことやら……。乞う、ご期待。
──前回に続いて「食と健康」というテーマで伺おうと思います。今回は、5歳の男の子のパパでもある為末さんの「食育」についての考えから、まずはお聞かせいただけますか?
為末:そうですね。うちの子の場合、ちょっと変わっているんですが、2歳とか3歳の頃まではブロッコリーとか、おにぎりとか、人参とかしか食べない子だったんです。あと、ソーセージとかも好きだったかな。かかりつけの医師の先生にも随分、相談しましたが「成長していく中でなんとかなりますよ」という答えでした。一番ホッとしたのは「みそ汁がうまい!」と言ってくれたときですね。みそ汁の味が分かるようになれば、もう安心だ、という気持ちになりました。
──日本食って、やっぱり偉大ですね。
為末:そうなんです。欧米のアスリートに話を聞くと、食ってガマンするものなんだそう。競技を終えるまで、ひたすら我慢して、食を摂生する。競技が終わった瞬間、フライドポテトみたいなものをこれでもかと食べる、みたいな。日本食には、そうした極端な誘惑はない。毎日、同じものを、おいしいなーと味わって、それで健康になっていく。息子が、みそ汁がうまい、と言った瞬間、とても安心したというのは、そういうことなんです。
──よく、分かります。
為末:食育の後半は、いうなれば「理性の食育」なんです。こうこう、こういう理屈だから、こういう食事をしろ、みたいな。でも、前半はネイティブというか、「感性の食育」なんです。なんだろう、舌の記憶みたいなものかな。僕は広島の出身なんですが、やっぱり瀬戸内海の魚の味とか、人生で最初においしいな、と感じた味に触れるとなんだかホッとするというか、体の芯から満足感が広がります。そうした感情が息子にも芽生えたんだ、ということは親としてとてもうれしく思います。
──話をまったく違う方面に振りますが、一方で、われわれ現代人は「食に縛られ過ぎている」ようにも思います。ダイエットとか、グルテンフリーとか、ベジタリアンとか。あれをしてはいけない、これをしてはいけない。とにかくストイックに、自らを律することが正義なのだ、みたいな。
為末:難しいお話ですね。(笑)
──「衣食住のバランス」といいますか。昔の家庭って、なんとなく三つのバランスがとれていたような気がするんですよ。大金持ちの家庭は別として、いわゆる庶民は、これを着て、これを食べて、こういう住まい方をしていれば幸せだよね、みたいな。決してぜいたくではないけれど、夕食のちゃぶ台には、カボチャの煮物があって、ひじきの煮付けがあって、おしんこも添えられていて、といった感じだったと思うんです。それが今では、会社や学校から帰ってきて、一人でパスタをゆでて食べる、みたいなことになっている。これだけ豊かになったというのに、食生活はなんだか貧しくなる一方であるような気がするのですが。
為末:それでいうと、中国人の友達に聞いたんですが、中国でも外食が基本になりつつあるみたいですよ。満漢全席とまではいかなくても、中国の家庭の食卓って、びっくりするほどの皿数が並ぶ、みたいなイメージがあるじゃないですか。
──そう思ってました。イタリアとか、韓国とかも、そんなイメージです。
為末:アスリートがお世話になっている栄養士さんには、二つのタイプがいるんです。一つは、知識系。理論的に、これはやるべきだとか、これはやってはいけない、みたいなアドバイスをくれる人。もう一つは、技術系。飲んでいいお酒とか、そのタイミングといった具体的なことを教えてくれる。知識系の栄養士さんは、どちらかというと理想を語るんですよ。それは分かるんですけど、その食材はどこで入手したらいいんですか?みたいな。一方で、技術系の栄養士さんは、コンビニで入手できるような食材でメニューを考えてくれたりする。
──なるほど。
為末:どちらが偉いとか、どちらが正しいということではないんですが、なんだろう、理想と現実のちょうど「中間」みたいなものを僕らは探っていかないといけないんだと思います。
(聞き手:ウェブ電通報編集部)
アスリートブレーンズ プロデュースチーム日比より
今回の取材の中でも、食をテーマに「理想と現実」「衣食住のバランス」「理性と感性」。為末さんの視点はバランスに満ちていると感じます。企業のパーパス/商品/サービス/プロダクトなどの開発においても、理想と現実、理性と感性、理論と実践のように、バランスを持って探ることが重要だと考えます。しかし、実際は、現実視点からの発想が多いのではないでしょうか。トップアスリートは、超越した領域に達したことがある人だからこその、振り切った視点を持っていると思います。企業の視点に、強制的に振り切ったアスリートの視点を統合した、納得解探しを、アスリートブレーンズとして邁進していきたいと思いました。
アスリートブレーンズ プロデュースチーム電通/日比昭道(3CRP)・白石幸平(CDC)
為末大さんを中心に展開している「アスリートブレーンズ」。
アスリートが培ったナレッジで、世の中(企業・社会)の課題解決につなげるチームの詳細については、こちら。