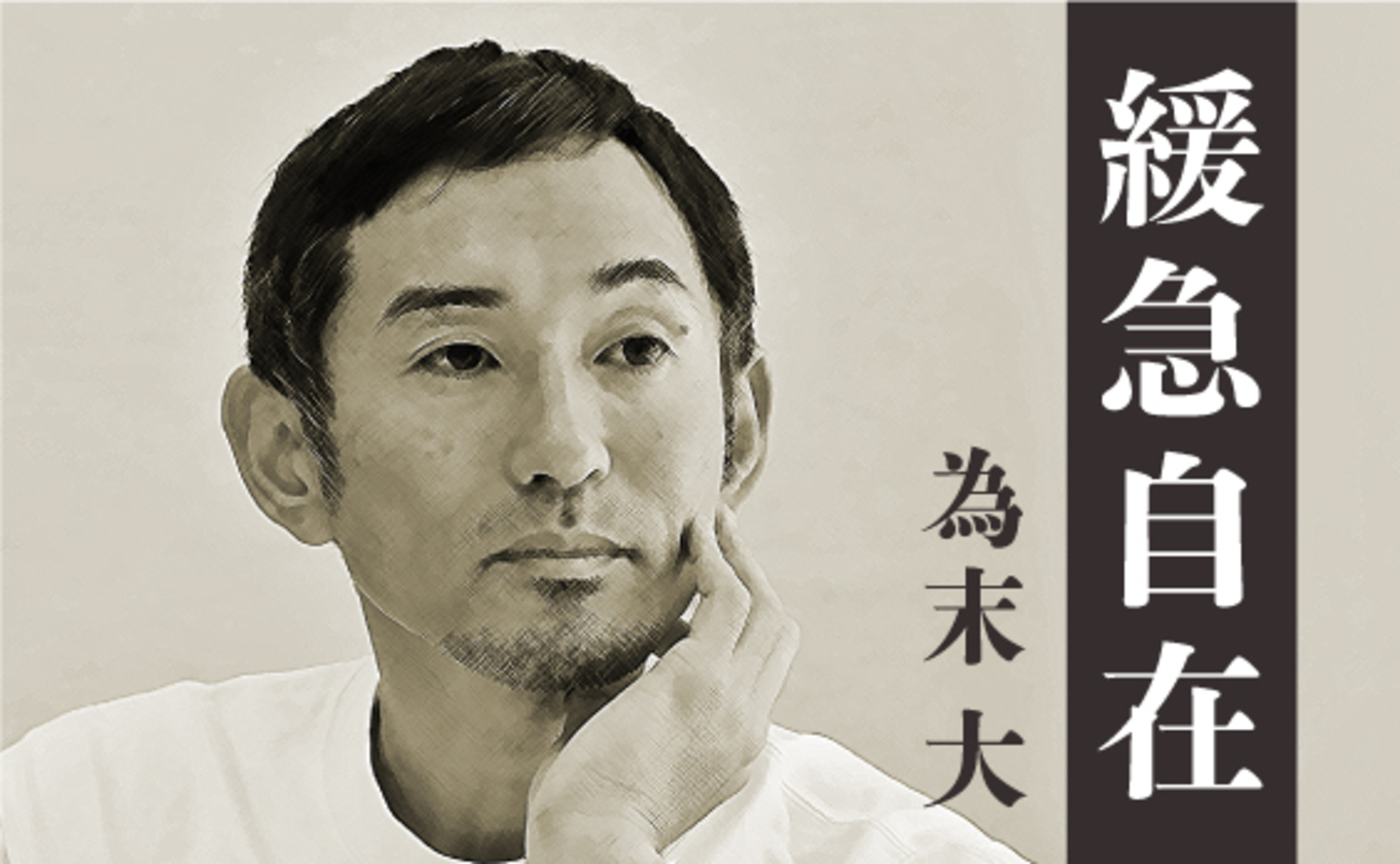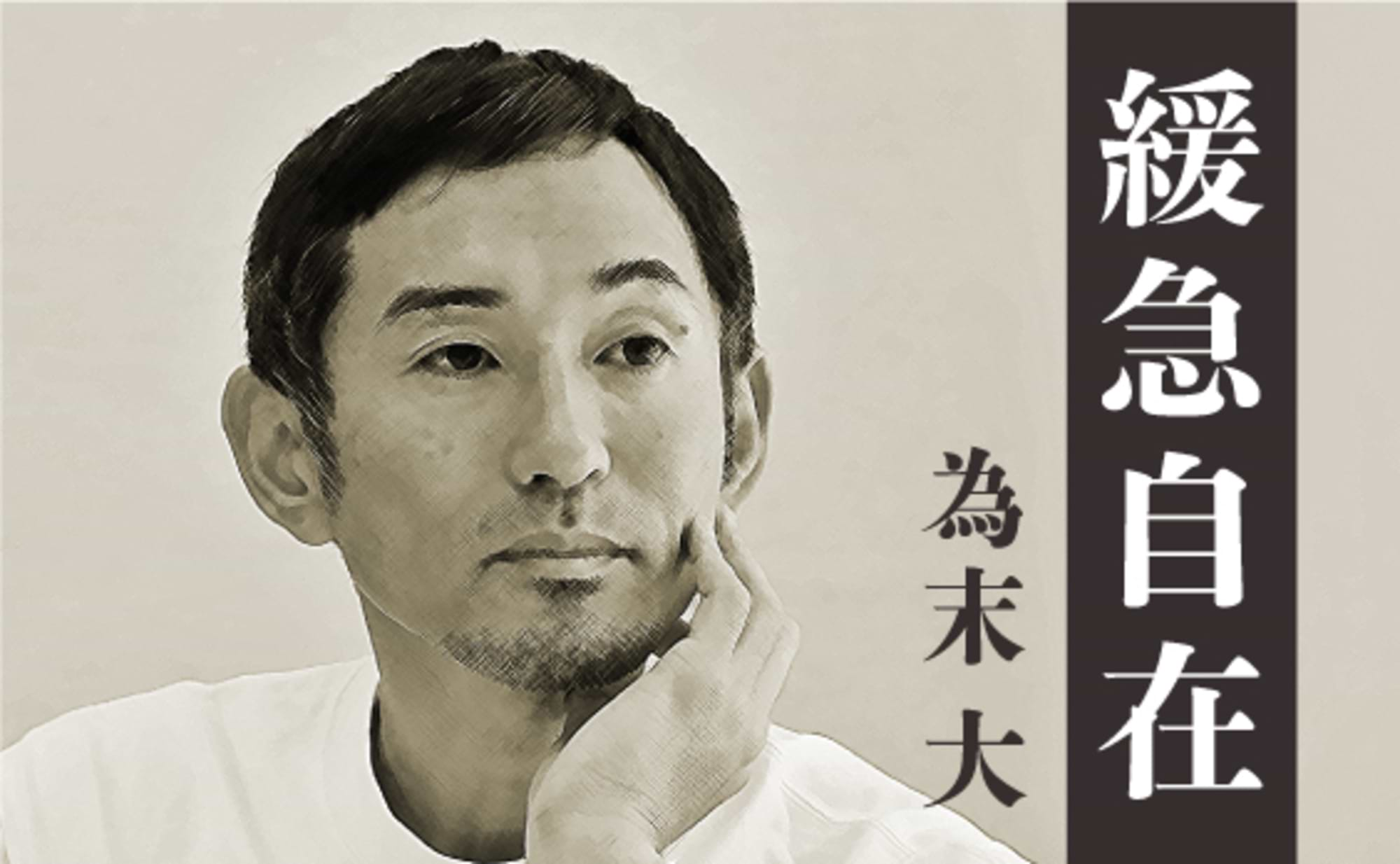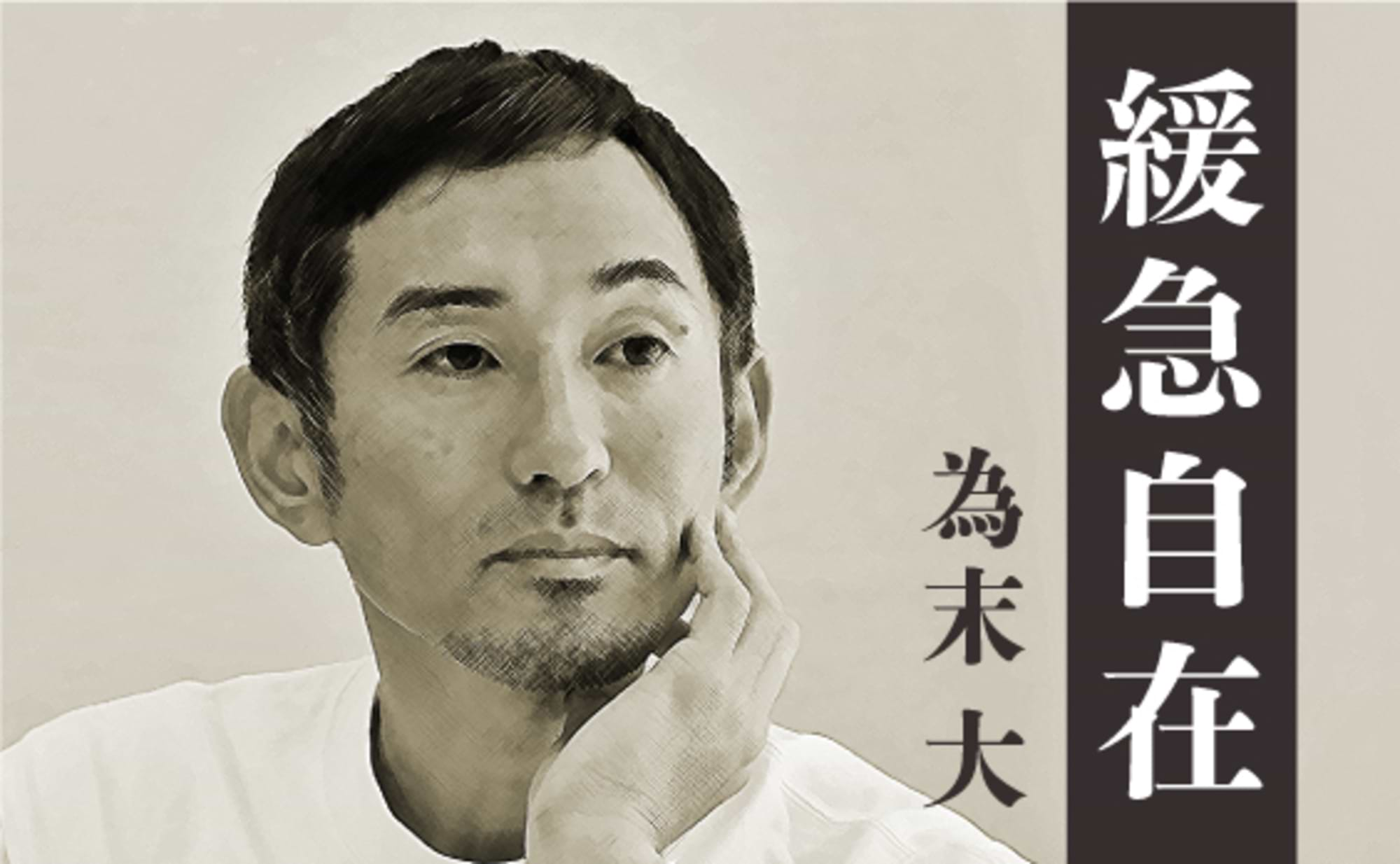為末大さんに「いま、気になっていること」について、フリーに語っていただく連載インタビューコラム。唯一、設定したテーマは「自律とは何か、寛容さとは何か」。謎の「聞き手」からのムチャ振りに為末さんが、あれこれ「気になること」を語ってくれます。さてさて。今回は、どんな話が飛び出すことやら……。乞う、ご期待。
──前回(#24)に引き続き、今回も「アスリートが見ている世界」というテーマにお付き合いいただきます。
為末:よろしくお願いいたします。
──前回は、為末さんのような孤高の陸上競技、あるいは柔道といった、いわゆる己の身ひとつで戦うアスリートの「物の見方」といったことについて教えていただきました。これが、たとえばサッカーやラグビー、バスケットボールといった「集団競技」になると「アスリートが見ている世界」は、どう変わるのでしょうか?
為末:集団競技の場合、「見る」ということに「時間」ということが大いに関わってきますね。
──時間、ですか。
為末:そう。目から得た情報を、すばやく短時間で読み取れる能力。察する力、と言い換えてもいい。ところが、です。さる大学教授の研究によると、たとえば日本の高校サッカーの選手とイタリアのプロリーグの選手の能力を比べたところ、ぱっと見、そんなに変わらないのだそうです。
──へえ、それは意外ですね。
為末:なのに、です。コンマ何秒、コンマゼロ何秒、コンマゼロゼロ何秒という世界で比較してみると、両者には天地ほどの差が出てくるらしい。つまり実力を分けるのは予測する力ではなく、予測する早さなんです。差を支配しているのは時間。その時間を操るのは、視力ではなく、直観力なんだと思います。そして、その直観力を高めるには……。
──状況を、ぼんやりと見る、ですか?
為末:その通りです。
──「ぼんやり」と、見るともなしに、見る。前回(#24)のキーワードでしたね。
為末:幼稚園児がやるサッカーとは、真逆の世界ですね。園児の場合、すべての子がボールを見ている。ボールだけを目で追っている。プロは、ちがう。チームメイトや相手選手、もちろんボールもですが、ピッチ全体を「ぼんやり」と見ていて、ここだ、というときに瞬時に、それも直感的に走り出してゴールを決める。
──いささか強引ではありますが、まさにこの連載のテーマである「緩急自在」ですね。
為末:この「ぼんやり」は人間でないとできないことだと思います。ぼんやり見るってのは意識と無意識が混在してなんとなく見ていることですから。AIは囲碁や将棋には人間に勝ちましたが、遠くを見ながら手元のコップをつかむということはまだ全く自然にはできないんです。
──なるほど。なんだかちょっと、うれしいな。「動体視力」にも、「ぼんやり見る」という能力は使われているのでしょうか?
為末:ぼーっと見る、という意味では当てはまらないかもしれませんが、「短時間で、直感的に見る」という意味では、近いものがあるでしょうね。ピッチャーが投げた球がストレートなのか、フォークなのか、スライダーなのか、ということをバッターボックスで判断するとき、「さあ、視点をどこに置こうか?」なんてことをやっている暇はないですから。その意味では、目というよりは脳で見ているのかもしれません。僕は野球の専門家ではありませんが、ボールをイメージではなく目で追っている選手は、超一流にはなれないんだと思います。
──「イメージトレーニング」が大事、とはよく言われることですが、「イメージ」というものが、今ひとつ「イメージ」できないんですよね(笑)。なので、どちらかというとハートの問題、みたいな精神論のほうに行きがち。でも、「脳で見ること」と言われると、なんだか腑に落ちた感じがする。
為末:たとえば、卓球の選手は「目」だけでなく、カツーン、カツーンというあの音を「耳」で見ているらしいんです。選手たちに言わせると、そんな覚えはありません!と口をそろえるらしいのですが。あと、似たような例でいうと、アスリートブレーンズのメンバーである朝原宣治さん(元陸上100m)は、スタートのピストル音を「耳」ではなく「背中」で聞く、という感覚でいたらしいです。
──どんな分野でもそうですが、鍛え抜き、感覚が研ぎ澄まされると、体のあらゆる部分が「目」や「鼻」や「耳」になっていくのでしょうね。陶芸家の手のひらなんかには、無数の目がついていそうだし。
為末:逆に言うと、「目には映っているけど、見えていない」という現象も起きてくるわけです。たとえば、道に落ちている石ころ。目には映っていますよね?でも、言われるまで見えてはいない。それは「名前付けができていない」あるいは「名前付けする価値がないと脳が判断している」ということなんです。
──なるほど。あっ、500円玉が落ちている!というとき、人は黒目をしっかり動かして、それを見ますものね。
為末:企業が行っているマーケティングなども、それに似ているのかなと思います。「どれだけの人がそれを見ているのか?」「なぜ、あれだけの数の商品を店頭に並べているのに、見てくれないのだろうか?」「きちんと名前付けされていないことに、原因があるのではないか?」などなど。
──ウェブ電通報の記事らしくなってきました(笑)。(#26へつづく)
(聞き手:ウェブ電通報編集部)
アスリートブレーンズ プロデュースチーム日比より
アスリートの視線の第2弾。目で見ているうちは、一流にはなれない。耳で感じるのではなく背中で感じる。そのために、「ぼんやり」でいることが大切で、視力ではなく直感力。ビジネスの世界でも、優秀なビジネスパーソン(経営者も含め)は、もしかすると、数字/企画書/現場を目で見ているのではなく、直感的に見ているのかもしれない。
普段仕事をする中でも、何かがおかしい「違和感」をプランニングの起点にしている中で、「ぼんやり」と見てみる、そんなことを試したくなる対談でした。仕事の進め方、考え方に対しても、新たな視点をくれるアスリートブレーンズ。ぜひ、よろしくお願いします。
アスリートブレーンズプロデュースチーム 電通/日比昭道(3CRP)・荒堀源太(ラテ局)
為末大さんを中心に展開している「アスリートブレーンズ」。
アスリートが培ったナレッジで、世の中(企業・社会)の課題解決につなげるチームの詳細については、こちら。