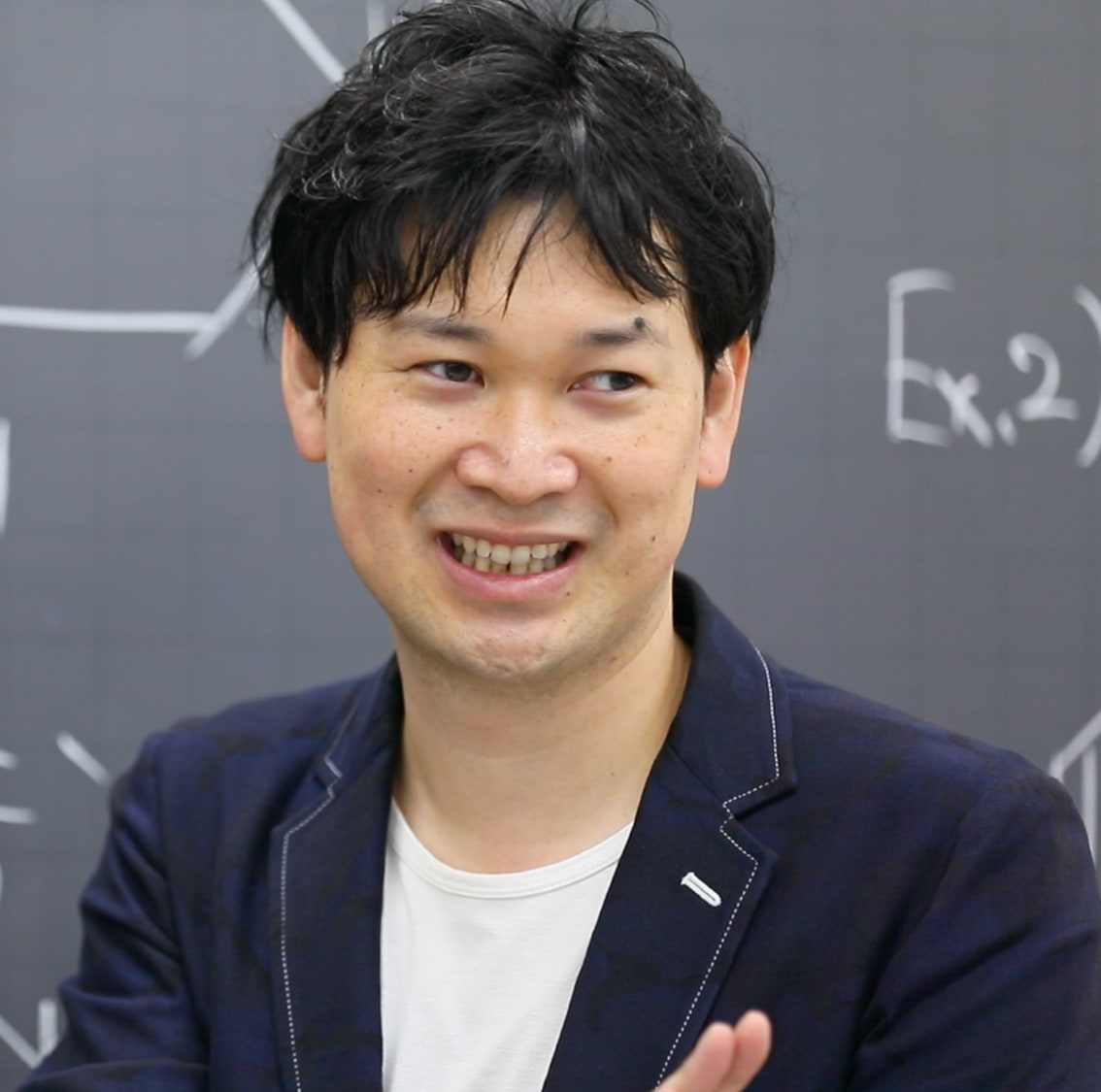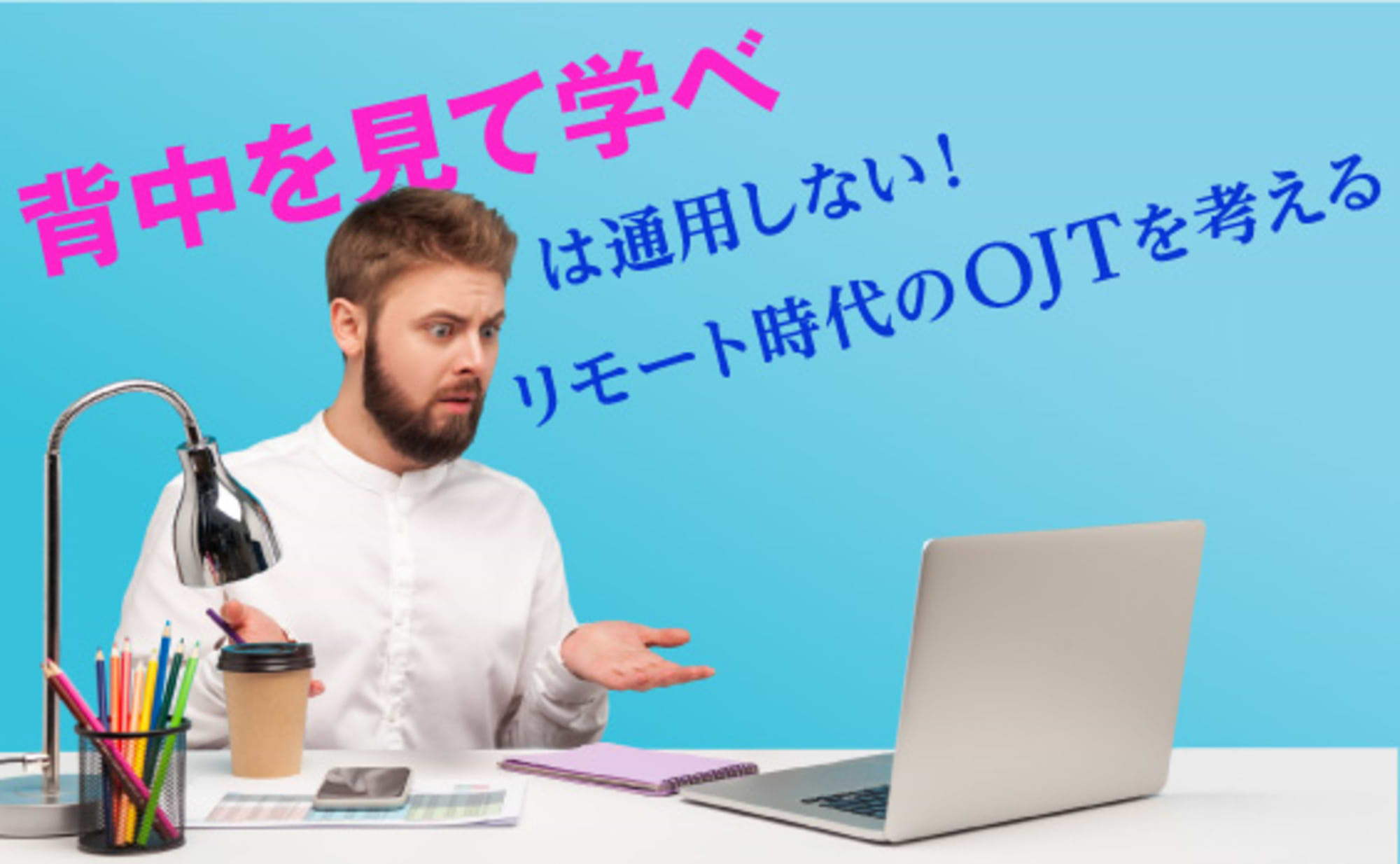2021年9月27日、電通トランスフォーメーション・プロデュース局とFunTreによるウェビナー「テレワーク時代のOJT再開発 "背中を見て学べ"をどう超えるか」が開催されました。
あらゆる業界でリモートワークが導入され、従来のOJTでは教育が行き届かないシーンや、「先輩の背中を見て学ぶ」機会の減少に悩んでいる企業の方が増えています。
リモートワーク環境でのOJTはどうあるべきなのか。そのヒントを探るべく、育成のプロフェッショナルをゲストに迎え、コロナ禍の人材育成に注力する電通の取り組みを交えながらディスカッションが繰り広げられました。
登壇したのは、のべ数百人の企業の人事・育成担当にヒアリングを実施し、アカデミックな知見をベースにニューノーマル時代の新しいOJT導入のソリューションを提供してきた犬塚壮志氏、電通人事局キャリアデザイン・プロデューサーの半田友子氏、リモートワーク下での新しいOJTの方法にトライし続けている電通の戦略プランニングディレクターの佐藤真木氏、そして2021年4月にリモートワーク下で電通に入社した鈴木舞氏。
それぞれの視点から、「背中を見て学べ」を超えるOJTのあり方について語り合いました。

犬塚 壮志氏:株式会社士教育 代表取締役 教育コンテンツプロデューサー。No.1予備校講師/東大院生として教育の専門家・アカデミック視点から企業人事と研修開発、育成プログラムの開発・講師指導を行う。
半田 友子氏:株式会社電通 人事局 キャリアデザイン・プロデューサー。労働環境改革が進む中、「全社員対象の成長支援策」の企画・運営を担当。社外有識者とともに学習コンテンツ開発を推進、半年間で約70講座を企画プロデュース。
佐藤 真木氏:株式会社電通 第3統合ソリューション局 コミュニケーション・ディレクター。ベテラン社員の経験知を言語化し、シェアを促進するプロジェクトを企画。OJTを中心とする現場教育のスペシャリスト。リモートワーク下の新人や若手社員の育成に注力。
鈴木 舞氏:株式会社電通 第2統合ソリューション局 ソリューション・プランナー。大学生時代の専門は、プロダクトデザインとブランドデザイン。リモート環境下の新入社員として「自分価値」をどのようにつくることができるかを模索中。
リモート環境で噛み合わない、ベテラン/中堅の「話したい」と若手の「聞きたい」
第1部は「現場教育の実践」をテーマに、リモート環境下で新しい現場教育にチャレンジされている佐藤氏、そして実際にその教育を受けた新入社員の鈴木氏が活動内容や実施後の感想などを話しました。モデレーターは犬塚氏が務めます。
犬塚:はじめに、リモート環境下の現場教育に何が起きているのか、佐藤さんからご説明いただけますか?
佐藤:現在、現場教育には3つの状況が生じています。それは、「リモートワークでやりやすくなったこと」「リモートワークでやりにくくなったと自覚できること」「リモートワークでやりにくくなったと自覚できないこと」です。
例えば、リモート環境だと場所を問わずにオンライン会議ができますし、このウェビナーのように動画を通して知見の共有がしやすくなりました。
逆にリモート環境では対面での丁寧な指導が難しく、親睦を深める機会も減ってしまったと感じる方が多いと思います。
こうした状況に対処することも大切ですが、私は3つ目の「リモートワークでやりにくくなったと自覚できないこと」をどう自覚して対処するかが非常に重要だと考えています。
例えば、毎日のようにオンライン会議を重ねる中で、ふと「リモートワークでみんなの話が長くなったかも?」と感じたことがありました。それはもしかすると、ベテラン/中堅社員の方が「自分が話し足りていないことに、自分で気づいていない」のかもしれません。若手社員のほうが圧倒的に話し足りていないにもかかわらず、つい先輩のほうが丁寧に説明しようと話し過ぎてしまうケースがあると気付きました。
犬塚:確かに、画面越しだと会話の流れといいますか、キャッチボールの質が少し変化する気がしますよね。その点、鈴木さんは入社当初からリモート環境下でOJTを受けてきたと思いますが、率直な感想はどうですか?
鈴木:やっぱり、先輩方とお話する機会が圧倒的に少ないので、先輩のいろんな考え方や価値観にもっと触れたいと率直に思います。それから、私たちはオンラインの働き方しか知らないので、先輩方がオンラインで何を伝えられて、何を伝えられないと感じているのか、それすらも分からないことに、もどかしさを感じています。
犬塚:ベテラン/中堅社員の「もっと話したい」という隠れた欲求と、若手社員の「もっと知りたい」という普遍的な欲求がうまくマッチングしていないという問題があるのですね。
ベテラン/中堅と若手が「主人公」になれる舞台を用意する
佐藤:そのようなミスマッチを解決するためのアクションとして、昨年から「武勇伝のナレッジ化」という取り組みにトライしています。これは複数のベテラン/中堅社員が持っているノウハウやこだわりなどの、いわゆる“武勇伝”を、若手社員がインタビューで引き出し、ナレッジとしてまとめて社内に共有する活動です。
犬塚:「武勇伝のナレッジ化」というタイトルだけでもワクワクしますよね。実は私も今年からこの活動に参加しているのですが、実際にやってみた感想をそれぞれの立場から教えてもらえますか?
鈴木:まず、日々忙しくされている先輩に「時間をください」と言うのはなかなかハードルが高いので、じっくり話を聞く機会を得られたことがすごくうれしかったです。また、共有していただいたナレッジを自分の中で噛み砕いて資料化するところまでやったからこそ、深く吸収できるものがあると思いました。
そして、何よりも会社の暗黙知というか、「会社の空気」みたいなものを初めて感じることができました。リモート環境だと「私は本当に会社に入ったのかな?」と思うこともあったのですが、この活動を通して、ようやく同じ会社の一員になれたと実感しています。
佐藤:インタビューされる側として感じたのは、話をしながら自分の中でも過去の整理ができて、「そういえば、こんな話もあったな」と、若手に話したいことが次々と生まれました。日々リモートでひたすら業務と向き合っていると、頭を整理する機会が意外となかったりするので、すごく良い機会になったと思います。
犬塚:ありがとうございます。それでは、今回の取り組みから得られた気付きを教えていただけますか?
佐藤:改めて実感したのは、オフライン中心世代とオンライン中心世代との間に、組織文化の「断絶」があるということです。その現実をしっかりと自覚した上で、ベテラン/中堅社員は組織文化の「語り部」となり、若手社員は組織文化の「継承者」となる。つまり、お互いが「主人公」になれる舞台を戦略的に用意してあげると、新しい循環が生まれ、主体性の発露につながるのではないかと思います。
「背中を見て学べ」ではなく、暗黙知の「言語化」が求められる時代
第2部は「人事の実践」をテーマに、犬塚氏と半田氏によるトークセッションが行われました。
犬塚:今回、なぜ人事の半田さんにOJTを問うのかというと、数年前から半田さんとお仕事をご一緒させていただく中で、人事=Off-JTと現場=OJTの関係性や、人事の人材育成のゴールに対する半田さんの考え方が面白いと思ったからです。改めてご説明いただけますか?
半田:人材育成のゴールは、経営にインパクトをもたらす人材を育てることだと思います。そう考えると、Off-JTとOJTの教育が分業になっている組織構造は、本来のゴールからズレていますし、新入社員のための教育になっていないと感じます。
犬塚:そうですよね、半田さんのOff-JTは、現場の課題やニーズを起点に研修プログラムを組んでいる点が非常に印象的でした。そんな半田さんがリモート環境下で課題に感じていることは何でしょうか?
半田:一番の課題はタイムマネジメントです。オフラインだと立ち話で済む話もリモートでは全て打ち合わせの場を設ける必要があるので、うっかりすると1日が全部ミーティングで埋まる可能性もあります。そうならないために養わなければいけないのが、タイムマネジメント力です。
1日分のタイムマネジメントができるようになれば、1週間、1カ月、半年、1年のタイムマネジメントもできるようになっていくので、キャリアデザインにも関わる重要な能力ですよね。このナレッジをどう伝達していくかがポイントだと思います。
犬塚:私自身、予備校講師としてeラーニングを行う中で、ナレッジ伝達の難しさを感じています。そこはOJTの現場が抱えている課題と通じるものがある気がします。
半田:従来の“伝承型のOJT”は「背中を見て学べ」が通用しましたが、リモート環境でのOJTはそれができません。だからこそ必要になるのが、指導者の言語化作業だと思います。なんで自分はこの仕事ができるのか、なぜこの課題を攻略できるのか、そういった教える側の暗黙知をもう一度振り返り、言語化しておくことが欠かせません。
犬塚:なるほど、リモート下で教える側に求められる能力も変化してきているということですね。
やらされた感がある学びに意味はない
犬塚:もう一つ、予備校講師として課題に感じていたのが、主体的な学びを促すこと。特にリモート環境だと自発性をサポートすることがなかなか難しいと感じます。
半田:前提として、やらされた感のある学びは本人に何も残らないので、意味のある学びにするために自発性はマストだと考えています。それこそ、実際の現場で本人が悩みに直面したタイミングで最適な研修の場を提供できるとベストですよね。何とかしたいという気持ちで来てくれるので、本気度が高いほど吸収できるものも大きいというのが実感値としてあります。
犬塚:確かに、半田さんと一緒に研修用のプログラムを開発した際も、現場で活用することを前提にテーマをかなりミクロに分けて動画を作りましたよね。Off-JTのプログラムでありながら、かなりOJT寄りだったなと。
半田:そうですね。これからはOff-JTとOJTが互いに補完し合ったり、越境したり融合したりするのが人材育成の目指すべき姿だと思います。
犬塚:リモートワークが定着したことで、今後ますます各企業でeラーニングの機会が増えてくると思います。その際に必要なコンテンツを改めて教えてください。
半田:一つは「言語化/説明スキル」です。リモート環境だとテキストのコミュニケーションが中心で、ウェブ会議でも空気感が伝わらないこともあるので、端的に説明して相手を納得させるスキルが求められると思っています。これはもちろん、教える側にも必要です。先ほど申し上げた暗黙知の言語化も大事ですし、第1部で佐藤さんが言っていたように、自分自身のスキルの棚卸しや、キャリアの可視化にもつながります。
もう一つが、タイムマネジメント力です。弊社でも3年前から取り組んでいるのですが、最近は特に現場からのニーズが強くなっていると感じます。タスク分解や、やらないことを決める方法など、教科書的なコツを新入社員に一度しっかりとインストールしていただくことが大切だと思います。
犬塚:最後に半田さんが考える人材育成の理想像を教えていただけますか?
半田:「社員全員が先生で、全員が生徒」のような状態になるのが理想です。「ここが分からない。ここを教えてほしい」という人がいたら、「それ得意。教えます」という人が自然に集まって、みんなで学び合う。シェアハウスみたいなことが実現できたらいいなあと思います。
犬塚:ありがとうございます。私自身もすごく勉強になりました!
「武勇伝のナレッジ化」モニター募集中!
電通と士教育は現在、ベテラン社員のナレッジシェアに関する新サービスを開発中です。
今回ご紹介した「武勇伝のナレッジ化」をフロー化。人材の選定から新人・若手向けのインタビュー研修、インタビュー実施までをフォローします。その後、インタビューの書き起こしを魅力的な「教材」にまとめ、共有しやすい場所・形式で格納します。
ベテラン社員に割いていただく時間はわずか1時間。思わずクリックしたくなるような表紙、中身も文字の羅列ではなく、ワクワクする企画書のような仕上がりになります。
現在、「武勇伝のナレッジ化」のモニター募集を受け付けております。ご興味のある方は、お気軽に下記までお問い合わせください。
https://hidenc.funtre.co.jp/