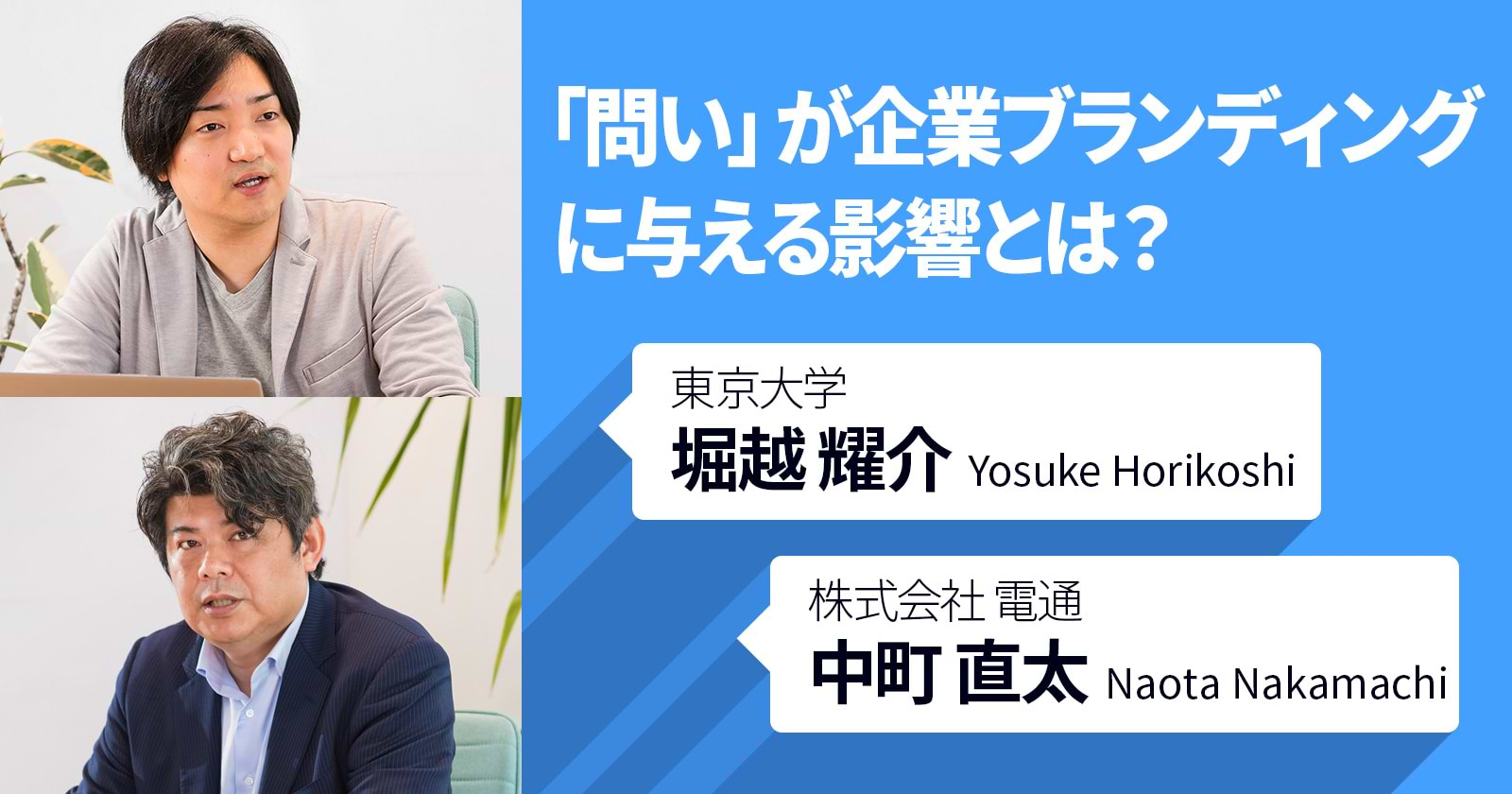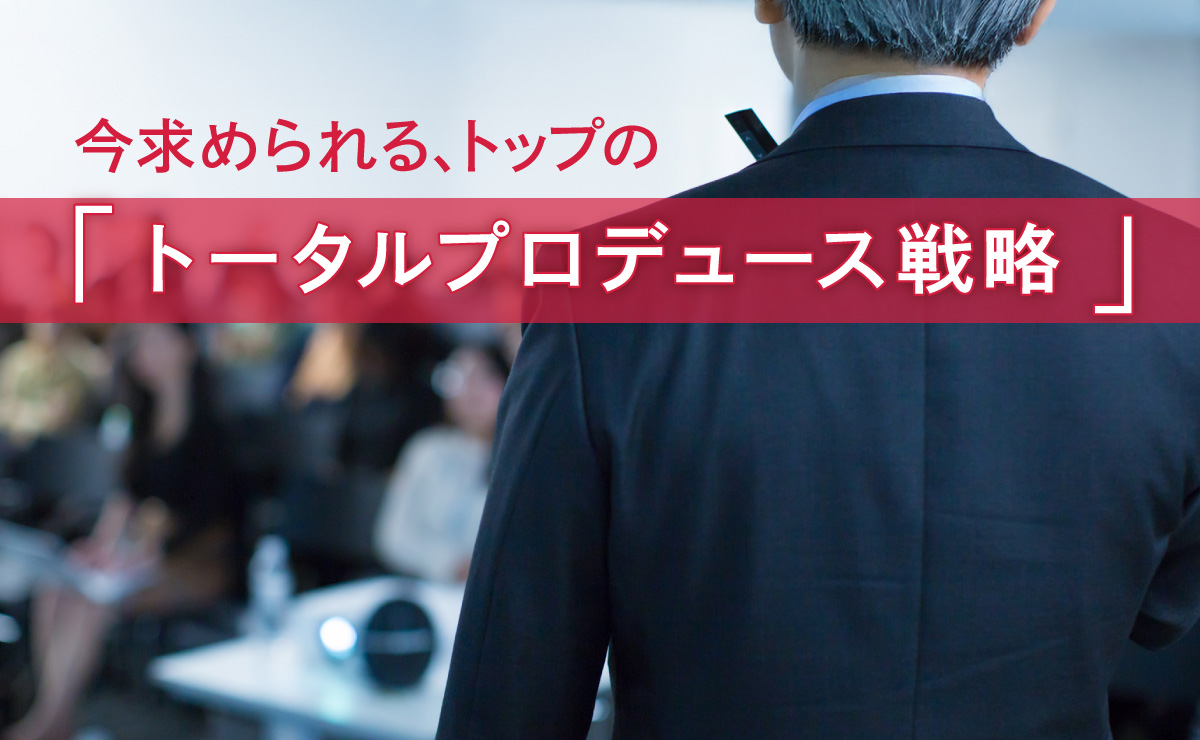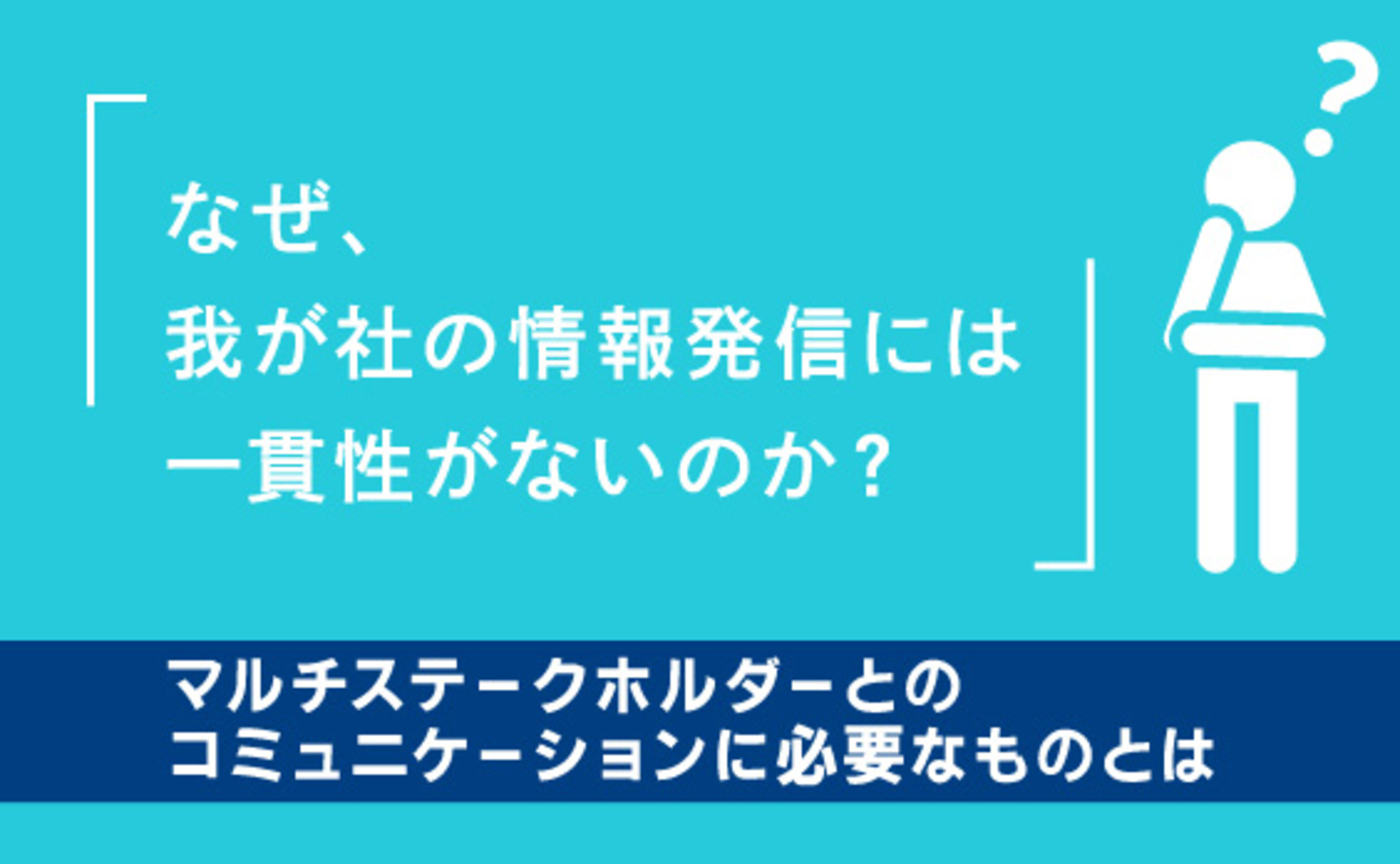企業の「パーパス」を社員に浸透させるために。哲学対話というアプローチが果たす役割とは?(後編)
企業価値の向上や社員の意欲喚起に役立つ「マイパーパス」。その策定を手助けするため、東京大学 共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生寄付講座 特任研究員の堀越耀介氏と株式会社 電通は共同で、「哲学対話」を用いた、「マイパーパス策定プログラム」の提供をスタートしました。
哲学対話の実践者でもあるUTCPの堀越耀介氏と、プログラム開発を推進した電通の中町直太氏のインタビューの前編では、プログラム立ち上げの経緯とサービスの概要を紹介しました。後編となる今回は、このプログラムによって生まれるブランディングの変化や、哲学対話の活用についての今後の展望などを紹介します。
哲学研究者×電通によって企業ブランディングは変化する
Q.前編でお話いただいたように、哲学対話という手法で社会への哲学の実践を試みている堀越先生の取り組みと、企業ブランディングの手法を模索していた中町さんの出会いが、今回のプログラムがスタートするきっかけでしたね。とはいえ、東京大学の哲学の研究者と電通がタッグを組むことに、かなり意外な印象を持たれることも多いと思うのですが、この2者のタッグだからこその強みとはどのようなものだとお考えでしょうか?

哲学対話の活用で、人や組織の可能性が広がる
Q.このプログラムをリリースしてから、どのような反響がありましたか。

Q.企業の活動のゴールはパーパスの達成になりますが、一方で短期的な利益確保も、活動し続けていくには重要です。場合によっては、この両者がなかなか両立しない、といった課題を感じているビジネスパーソンも多いと思います。そういった壁にぶつかりがちな読者に向けて、堀越さんからアドバイスはありますか?
Q.ありがとうございます。「問い」で組織を動かす、とてもいいですね。では最後に、「哲学対話」を活用した「マイパーパス策定プログラム」は、どのようなクライアントの手助けとなるサービスなのかをお話いただけますか?

これからの企業ブランディングにおいて、哲学対話やそこから生まれる問いは、人や組織の可能性を大きく広げるアプローチの1つとして、非常に興味深いものであることが分かりました。企業だけでなく、自治体や教育機関でも、哲学対話を活用したマイパーパスの策定や研修は、個人や組織の意識の変革、能力の向上に役立つことが期待されます。
※掲載されている情報は公開時のものです
この記事は参考になりましたか?
著者

堀越 耀介
哲学/教育学研究者 博士(教育学)
東京大学UTCP上廣共生哲学講座 特任研究員/独立行政法人日本学術振興会 特別研究員(PD)。東京大学教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。専門は、教育哲学、哲学プラクティス。実践者としては、学校教育や自治体・公共施設、企業・社員研修でも、哲学対話・哲学コンサルティングを行う。著書に『哲学はこう使う――哲学思考入門』(実業之日本社)、「哲学で開業する:哲学プラクティスが拓く哲学と仕事の閾」(『現代思想』(青土社)2022年8月号)などがある。

中町 直太
株式会社 電通
第4マーケティング局 ブランドコンサルティング部長
入社後、マーケティングプロモーション局、営業局を経て、現在は第4マーケティング局でコーポレートブランドコンサルティング/広報コンサルティングを専門とする。コーポレートブランドコンサルティング領域では、さまざまな業種の数万人規模の大企業やスタートアップ企業などを幅広く支援。特に、インターナルコミュニケーションによる企業文化変革支援が得意分野。またPR領域では、放送局のディレクターとしてテレビ番組の制作、そしてグループ会社設立時の広報体制立ち上げを経験。クライアントワークにおいては自治体の新条例の成立支援や、国際的なビッグイベントの広報戦略立案など、大型プロジェクトの経験も豊富。