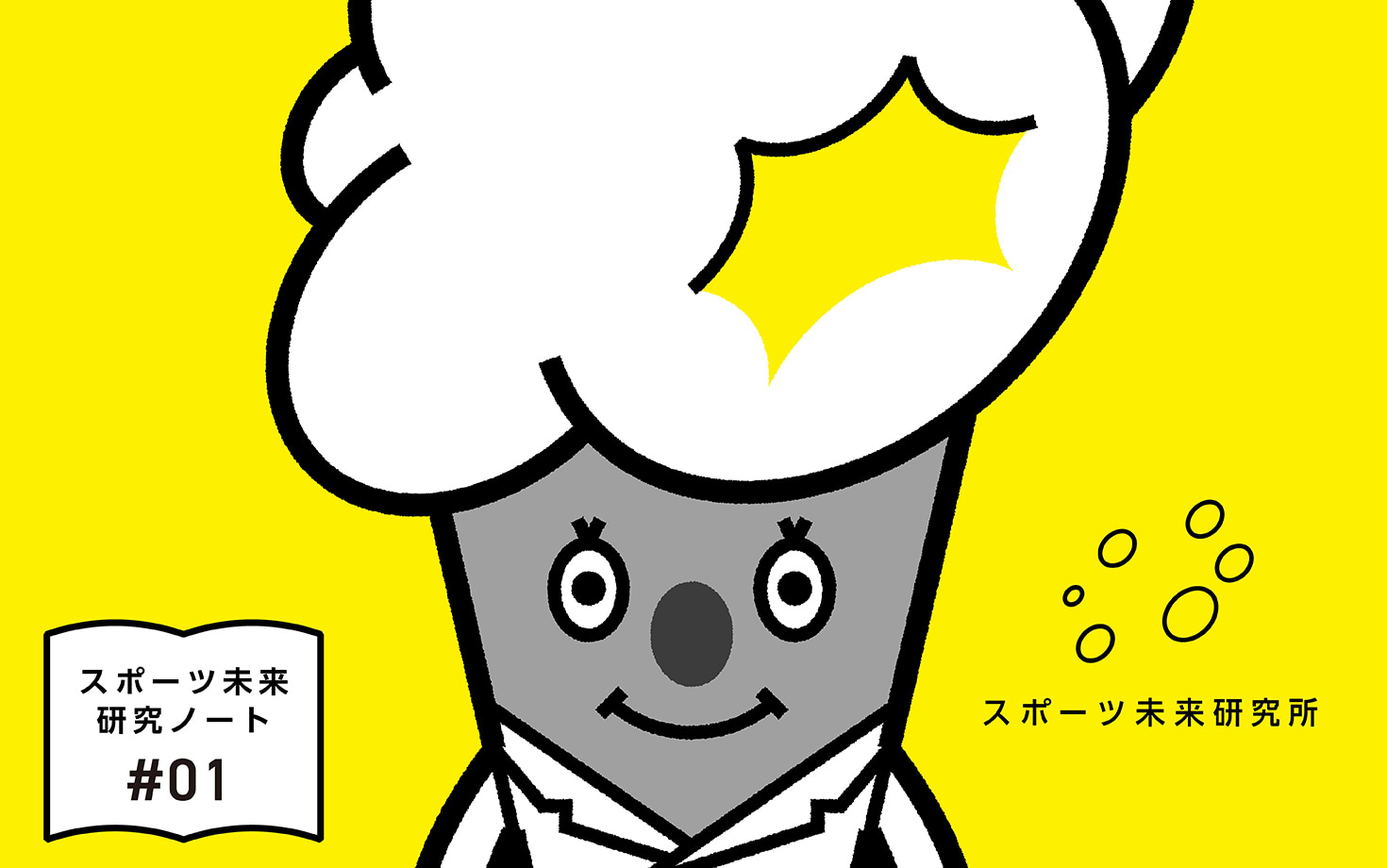「スポーツ未来研究ノート」、はじまります
「スポーツには価値がある」とよく言われますが、実際にどんな価値があるのでしょうか。また、それはいったいどれくらいの価値なのでしょうか。本連載「スポーツ未来研究ノート」では、そうした問いに対し、スポーツ未来研究所の研究員が、定性的、定量的に明らかにしていきます。また、「スポーツの価値」を明らかにする研究や取り組みも紹介します。
スポーツ未来研究所のミッション
スポーツ未来研究所は、「スポーツを、ひろげよう」をスローガンに、2025年7月に発足しました。背景には、電通が長年スポーツビジネスの現場に立ち続ける中で抱いてきた、「スポーツは、もっと自由に、もっと面白くなれる」という思いがあります。
スポーツを愛するすべての人が交差し、それぞれの知識や視点、熱が交わり、スポーツの新たな可能性をひろげていく。そんな場を目指しています。
所長には、パラリンピック・アルペンスキー元日本代表であり、電通フェローの大日方邦子さんが就任。電通がこれまで培ってきたスポーツビジネスの知見を生かし、未来志向でスポーツの真の価値の探究に取り組んでいきます。
定量的な価値を明らかにする研究
研究所として現在進めている最初のプロジェクトは、「スポーツ観戦の体験価値の可視化」です。これは、早稲田大学、東海大学、電通サイエンスジャムと共同で研究を行い、観客の感情の変化を脳波や心拍といったリアルタイムの生体情報を計測し、定量的に解明していくというもの。
スポーツ観戦の体験価値はアンケートやインタビューなど、定性的に捉えることが一般的ですが、共同研究では観戦中の「ワクワク」「ドキドキ」「ハラハラ」といった感情を定量的に捉え、これまで可視化できていなかった観戦体験の本質的な価値を明らかにすることを目指します。
さらに、スポーツ観戦特有の「感情のシンクロ」にも注目。スポーツ観戦には他者と感情を分かち合う瞬間が多くありますが、観戦スタイル──例えばスタジアムで仲間と盛り上がる、オンライン観戦でSNSを通じてつながるなど──によって感情のシンクロに違いがあるのか、また、感情のシンクロが観客のウェルビーイングやファン意識にどう影響するのかを探ります。
研究成果は、スタジアムの改善やスポーツコンテンツの進化、新しいエンターテインメントビジネスの最適化など、社会への還元を目指します。成果はこのスポーツ未来研究ノートでも紹介していきますのでお楽しみに。
インタビューを通じた定性的な価値の探究
スポーツの価値を定性的に探究していく切り口はいろいろあります。本連載ではアスリートや競技団体、スポーツ科学の研究者・有識者などへのインタビューを通じて、それぞれの専門分野から見えるスポーツの価値や、インタビュイーにとってのスポーツの価値を深掘りしていきます。
ナビゲーターは、研究員・ポップくん
この連載のナビゲート役となるのは、本研究所の研究員であるキャラクター、ポップくんです。大学でスポーツについて幅広く学び、卒業後に当研究所の研究員になりました。新しいことを知るのが大好きで、考えごとをしているときや驚いたときに頭のポップコーンが「ポンッ」とはじけるのが特徴です。これから記事のあちこちで登場していきますので、どうぞよろしくお願いします。
今後の予定
「スポーツ未来研究ノート」は月1〜2回の更新を予定しています。
第2回:スポーツ未来研究所 所長 大日方邦子
第3回:早稲田大学 教授 佐藤晋太郎、東海大学 准教授 押見大地 共同研究「スポーツ観戦の共体験」について(予定)
「スポーツ未来研究所」のトピックスやお問い合わせはこちら
https://www.dentsu.co.jp/labo/sports_future/index.html

この記事は参考になりましたか?
著者

勝見 文一
株式会社 電通
スポーツビジネスソリューション局
シニア・ディレクター
2015年から東京2020 オリンピック・パラリンピックに専従し、スポンサーアクティベーション、聖火リレー、SPP(競技会場内演出)などをプロデュース。現在は、スポーツの価値の可視化と新しい価値の探究に取り組み、2025年7月、スポーツ未来研究所をスタート。日本スポーツ産業学会所属。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科在学中。沖縄生まれ、南米ベネズエラ育ち。