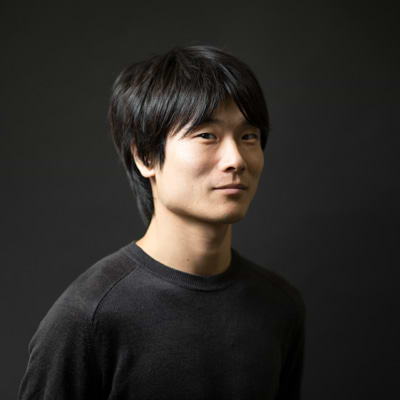2023年2月、企業のDX支援を行う株式会社GNUS(ヌース)は、大企業の管理職500名を対象に実施したDX調査の結果を公表しました。この調査結果から、「DXの成果に十分満足している企業はわずか6%しか存在しない」ということが判明。なぜDXの成果に十分満足している企業がここまで少ないのか、また成果に満足している企業としていない企業との差はどこにあるのか、本調査を実施したGNUSに立ち上げ時からビジネスアーキテクトとして参画し、さまざまな企業のDXに携わってきた栗林祐輔氏に話を聞きます。
「プロダクト開発」の視点で、DXの現状を調査
 株式会社GNUS 栗林 祐輔氏
株式会社GNUS 栗林 祐輔氏Q.まずは栗林さんの経歴を教えてください。
栗林:株式会社 電通に新卒で入社し、デジタルマーケティング部門を経て営業局に配属になり、ナショナルクライアントや外資系クライアントの担当をするほか、スタートアップのプロダクト企画や事業開発などにも関わっていました。その後、グローバル部門に異動となり新規事業やテック関係のプロジェクトなどを担当。そうした中で、GNUS立ち上げ時に現CEOの文分から声をかけられ、GNUSにジョインすることになりました。
Q.現在は主にどのような業務を担当されていますか?
栗林:GNUSでは、さまざまなクライアント企業さまのプロジェクトに対して、各分野のプロフェッショナル人材をアサインし、アプリやWebサービスなどのソフトウェア開発を行っています。私は、職種としては「ビジネスアーキテクト」といって、プロジェクト設計やプロダクト戦略の設計を担う役割です。お客さまのご要望を聞き、プロダクト開発に必要な調査やワークショップを企画する、ユーザーニーズの定義を行うなど、コンサルタント的な動きをすることもあります。
Q.今回、大企業の管理職の方々を対象に、自社のDXの状況や成功の理由について調査を行うことになったのには、どのような背景があったのでしょうか。
栗林:この調査を行う以前から、当社では、DXに関するさまざまなデータに触れる中で、自社のDXに満足していない企業が多いらしいということを把握していました。そうした企業に対して、GNUSとしてどのようなご支援ができるのかを明確にするためには、なぜうまくいかないのかをしっかりと分析した上で、具体的にどのようなサポートができるかを発信していくことが重要だと感じ、まずはDXに取り組む企業の現状を調査したいと考えたのです。
自社のDXの成果に十分に満足している企業は、わずか6%
Q.今回の調査で、栗林さんが特に注目したところについて教えてください。
栗林:まずは、DXの成果への満足度です。「十分に満足」と答えているのは、わずか6%。しかも、回答者の半数以上が2年以上DXに携わり、年間1億円以上の予算をかけているということを考えると、成功確率としては非常に低いということが分かると思います。

Q.DXに満足している企業と満足していない企業には、どのような違いがあるのでしょうか。
栗林:1つは、具体的なプロダクト・サービスへの取り組みがあるかどうか、です。回答者を「DXに十分満足している企業」「十分に満足していない企業」に分けて、「DXにおいてプロダクトやサービスをリリースしたか」を聞いたところ、満足している企業は83%が何かしらをリリースしているのに対して、満足していない企業は23%という結果でした。また、リリースしたらそこで終わりではなく、改善を重ねていくことも重要だと分かりました。DXに満足している企業の多くが継続的に改善・アップデートしているのに対して、満足していない企業は改善・アップデート率が低く、既にリリースしたサービスを終了しているところもあるという結果が出ています。
さらに、うまくいっている企業の40%が、1~2週間に1度以上というハイペースでアップデートしています。特に、デザインなど細かな部分の修正に関しては、多くの企業が実施しているようですが、「ユーザビリティの調整・改善」や「新規機能の追加・拡張」といった、よりサービスの根幹に関わるような見直しについては、うまくいっている企業の方が積極的に取り組んでいるようです。こうした結果を踏まえると、やはりユーザーからのフィードバックを受け、1つひとつ改善していくことが肝になると言えます。

Q.理念や計画だけが先行するのではなく、具体的にサービスを開発し、世に出し、適宜アップデートしていくことが、DXの成果を高めるために重要だということですね。他にも、何かポイントはありましたか?
栗林:ユーザーニーズを汲み取ることも、DXの成功を決めるファクターになっているようです。「DXを検討する上で重視すべきだと思うことは?」という質問への回答を見ると、うまくいっている企業はどの項目への意識も高かったのですが、特に「プロダクト・サービス内容の継続的な改善」「ユーザーニーズの理解」「ビジョン設定」に対する意識が高くなっていました。
また、「課題・障壁」に関しては、うまくいっている企業・いっていない企業ともに「ユーザーニーズの理解」が最も難しいと回答しているので、これは当社としても注力していくべきところだと感じています。
では、ユーザーニーズを理解するためには、何をすべきなのか。「ユーザーニーズ理解のために重視していることは?」の回答を見ると、「実利用データ分析」や「定量アンケート」は、うまくいっている企業でも、いっていない企業でも実施されているところが多いようですが、一方で「モックアップ・プロトタイプの作成」「アジャイルプロセス(短期間で実装・テストを繰り返しながら開発を進めていく手法)の導入」「エスノグラフィ調査(対象者と一定期間生活を共にし、行動を観察する手法)・観察調査」などは、うまくいっている企業の方が高い割合で実践されています。この結果を見ても、データ分析だけではなく、実際にプロダクトを提示してユーザーの意見を聞く工程や、具体的なフィードバックを基に改善する工程がキーになっていると考えられます。

栗林:以上の結果から、DXの成果に満足するために大切なことが2つ挙げられます。1つは、具体的なサービス・プロダクトをリリースすること。もう1つは、ユーザーの生の声を積極的に聞き、取り入れることです。また、そうして作り上げたプロダクトを頻繁にアップデートすることも重要と考えられます。こうした発見を、GNUSがご提供できる価値とも重ね合わせながら、発信していきたいと思っています。
自社のDXの成果に満足している企業・していない企業の違いが明らかになったことで、DX成功のために必要な取り組みや心構えが見えてきました。後編では、栗林氏自身が数々の企業のDXに携わる中で感じている課題や、これからDXを推進していきたい企業に伝えたいことなどを聞いていきます。