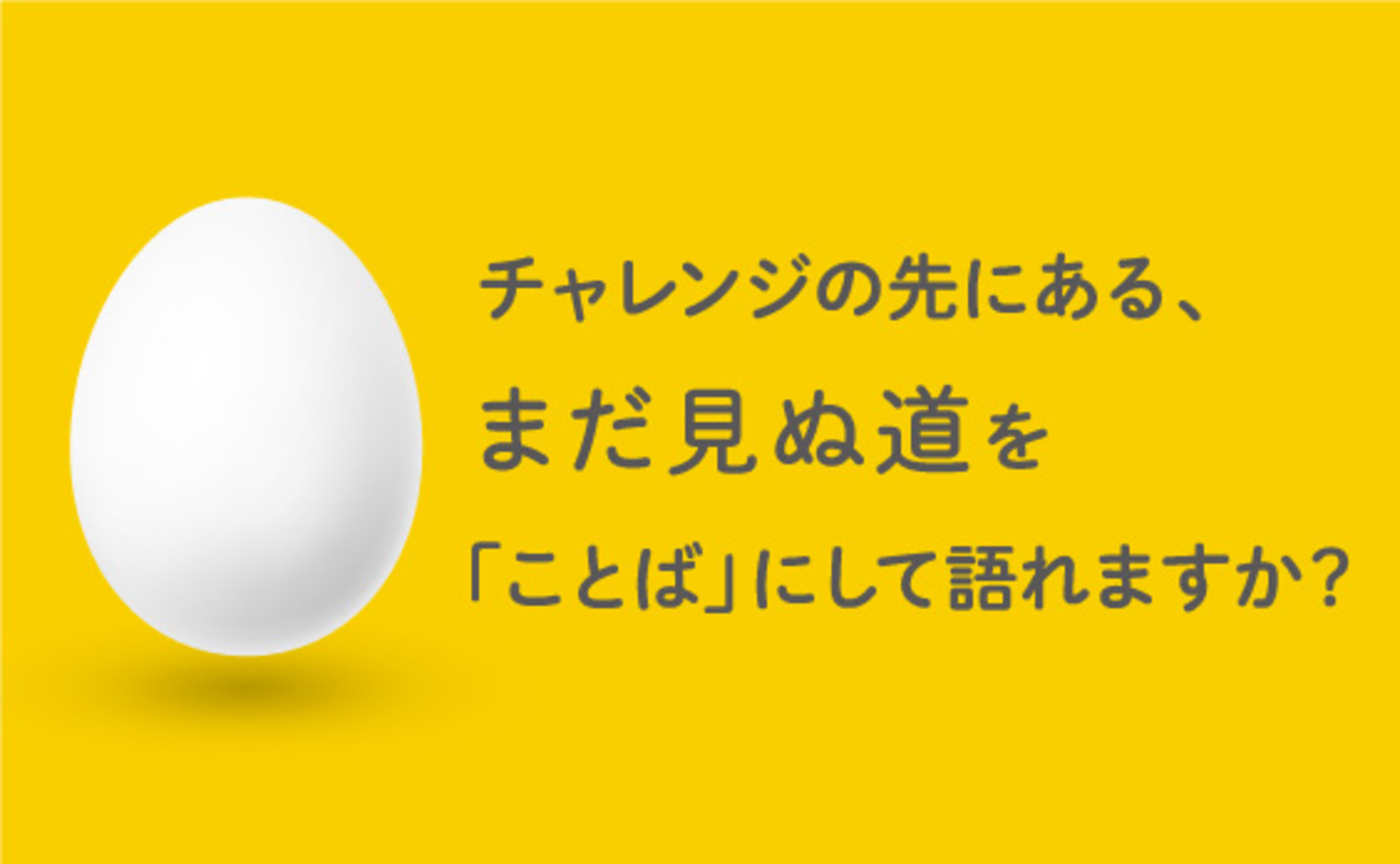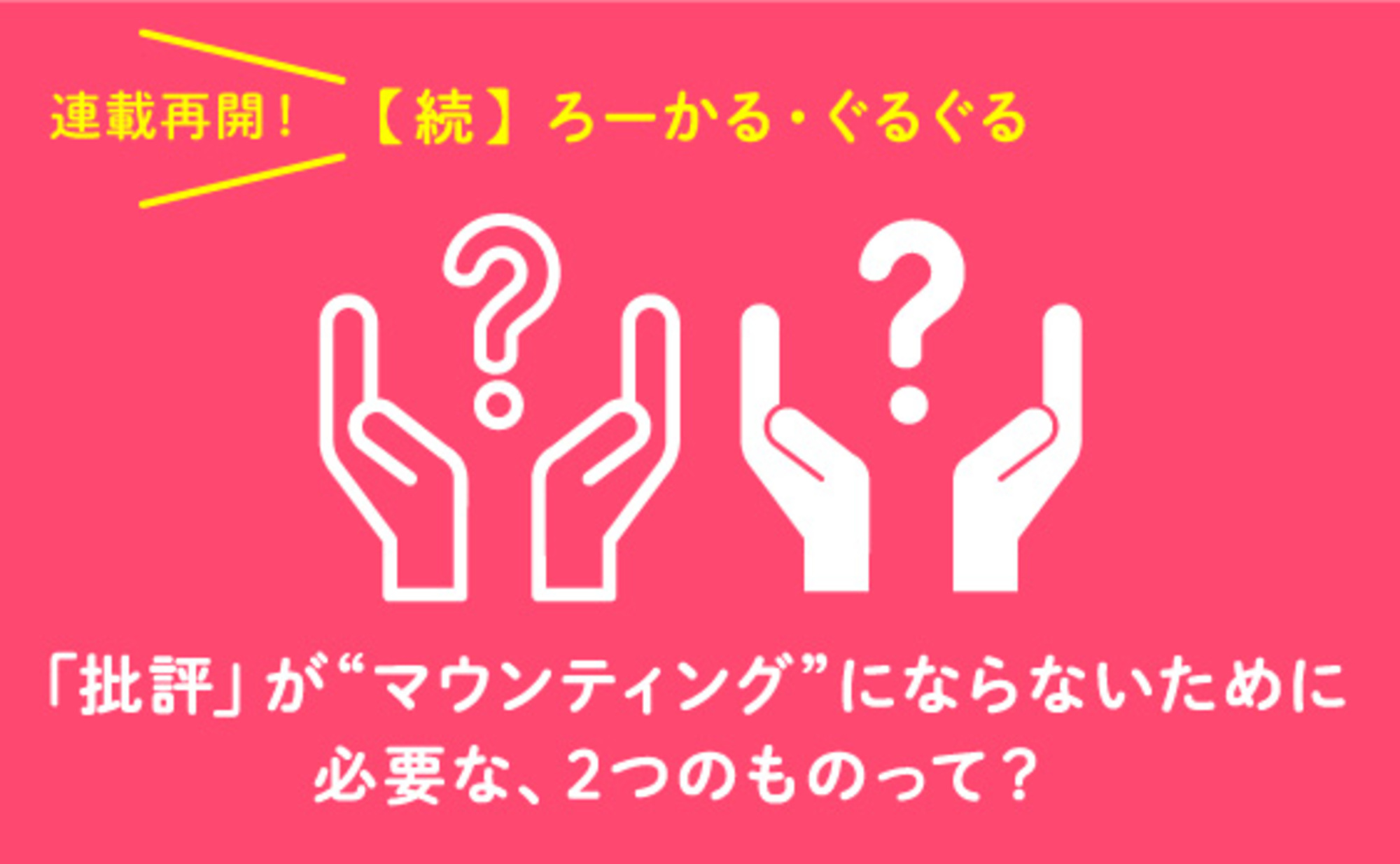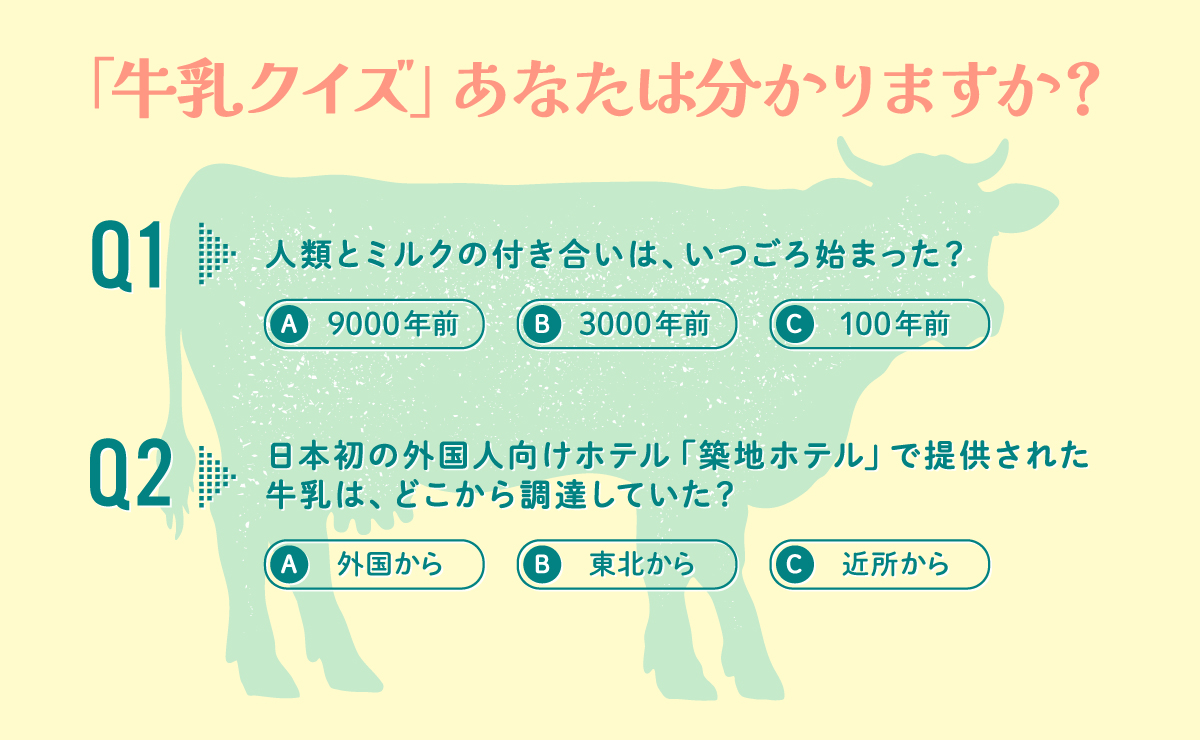もう師走。
街にジングルベルが鳴り響けば、食卓に上るのはローストチキンが相場ですが、なぜかわが家は昔から、煮鶏。

ご覧の通り、丸の鶏肉を野菜と一緒に煮込んだ料理です。味つけは醤油ベース。この和風とも洋風ともつかないレシピがどこから来たのかは謎ですが、最大のポイントは、いわゆる「スタッフィング(つめもの)」。もち米、タマネギ、ニンジン、シイタケ、松の実、レバーを細かく刻んで詰めます。
ただ、これにふっくら柔らかく火を通すことが至難の業。長い時間をかけて煮込めば良さそうですが、そうすると今度は外側の肉がとろとろに溶けてしまうのです。とにかくあんばいが肝心。大まかなレシピは書き起こしてあるのですが、毎年精肉店で手に入る鶏のサイズも違うし、年に一回のチャレンジではなかなかコツもつかめないし、今度のクリスマスも結局、米寿を迎えた母の腕前に甘える予定なのであります。

閑話休題。
ここで一年を少し振り返ってみると、今年もまた、ビジネスの場でよく話題となったのが「パーパス」でした。日本企業の長期低迷やコロナで変化した生活者との関係を解決する切り札として「いまこそ、パーパス」なんて話も聞きました。
一方で、社長以下、大きな労力をかけて設定したものの、ちょっと時間がたってみると結局何も変わっていないことに気がついて、いわば“パーパス疲れ”のような状態に陥っている組織にも出合いました。
あるいは「アジャイル開発」。どのようなプログラムを開発したいのかという全体計画を確定させてから開発に取り掛かる「ウォーターフォール」ではなく、短期間の開発サイクルを反復させる中で、顧客からの要望などに柔軟な対応をする「アジャイル」方式を採用しようという動きも盛んでした。そういえばデザイン思考でも「ラピッド・プロトタイピング」(※)を推奨していたからと、準備不足のまま市場に飛び込み、結果、にっちもさっちもいかなくなっているケースも目撃しました。
※ = ラピッド・プロトタイピング
製品開発の過程で用いられる手法で、試作品を短時間でつくりながら、課題等を考えるアプローチのこと。
なぜ、こんなことが繰り返されてしまうのでしょう?
経営学者、野中郁次郎先生は、書籍「直観の経営 『共感の哲学』で読み解く動態経営論」における哲学者、山口一郎先生との対談の中で、次のようなことをおっしゃっています。

以前に比べれば、もう「ハウツー」は通用しない、これからビジネスパーソンはリベラルアーツを学ぶべきだ、ということがいわれていますね。(中略)
とはいえ、リベラルアーツといわれる哲学にしても、歴史にしても、それらを学ぶこと自体が目的となってしまえば、結局それはハウツー的な教養にしかならないし、生きていくうえでの人々の血肉にもならないはずです。
昨今は、デザインシンキングという考え方が流行りですね。ロジカルシンキングではなく、デザイナー的視点のクリエイティブな思考で問題を解決するのが大切、というわけですが、結局はそれもハウツーに回収されていくことはありえないか。本来そこでは、「そもそも教養とは何か」「人間が知性をもつとは、どういうことか」という本質を徹底的に考え抜く必要がありますが、そうした問題意識がとくにいまの経営学には、欠落しているように思えてなりません。
(「直観の経営 『共感の哲学』で読み解く動態経営論」<野中郁次郎・山口一郎著 KADOKAWA>)
少し長いですが、とても重要な指摘なので引用しました。たとえば、ぼくらはパーパスを設定すること自体が目的になっていなかったか?「ワクワク」するパーパスと、ロジカルシンキングやPDCAといった客観的手法との関係を本当に考え抜いただろうか?そもそも「組織とは何か?」「組織を動かす原動力とは何か?」という本質に触れないままで、パーパスが機能することなどあり得るのだろうか?
パーパス、デザイン思考、アジャイル開発に限らず、ぼくたちは数多(あまた)のバズワードを経験してきました。そしてその多くは本質を理解されることもなく、ハウツーに回収され、忘れ去られていきました。もう、この不幸な繰り返しをやめませんか?
とんでもない大風呂敷を広げてしまいましたが、実はいま、社内の仲間と「企業組織がイノベーションを加速するための新サービス」を準備中です。
ここでは新鮮さをアピールする派手な概念を示す代わりに、「組織とは何か?」「組織を動かす原動力とは何か?」「クリエイティビティとは何で、それは組織活動のどんなタイミングで必要とされるのか?」といった基本的な問いにも、真正面から挑戦しています。結果、いままでの取り組みとは本質的なところで全く違うものになったと自負しております。
この新サービスについては、次回、新年のコラムでご紹介する予定です。
どうぞ、召し上がれ!