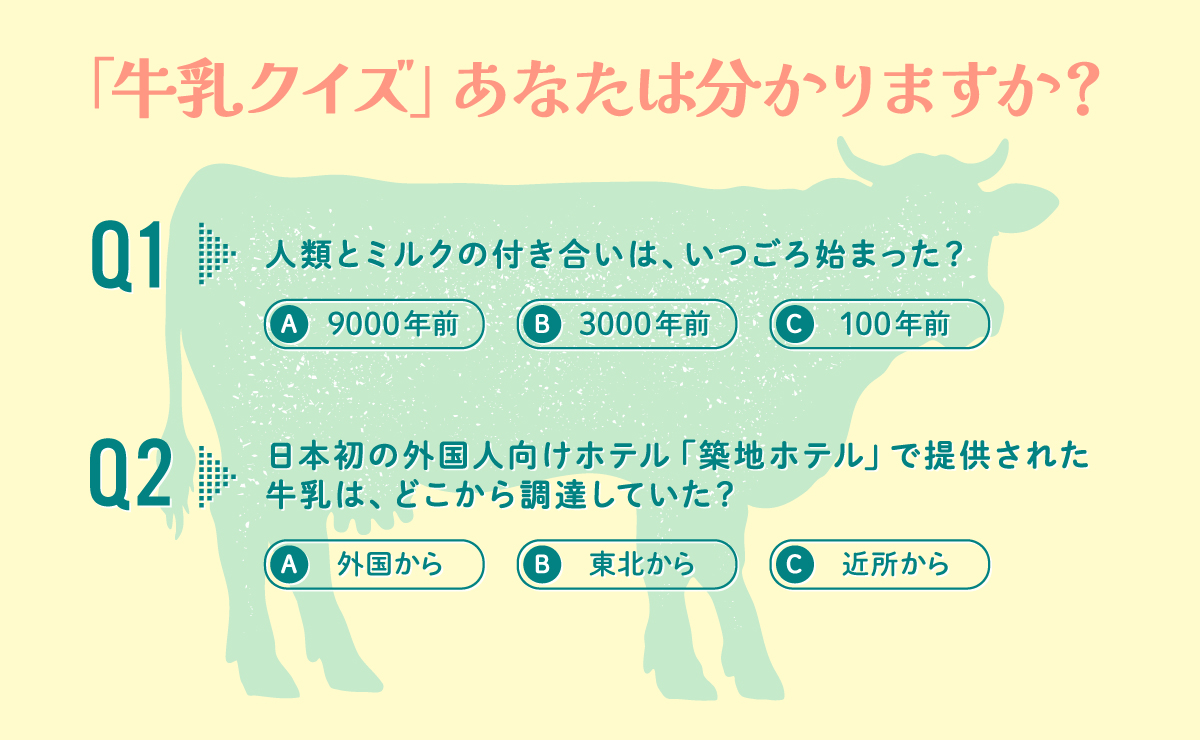熊本を中心とした地震で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
料理は大好きなぼくですが、ひとつ大きな弱点があります。それは「カレーライス」。恥ずかしながら、「カレールウ」を使って料理した経験がないのです(小学校2年生の時、泊りがけの遠足でみんなと大鍋につくったことがあったかなぁ)。もちろん嫌いじゃありません。ただ酒の肴にもならないし、わざわざつくる機会がないだけです。カレー粉を使った煮込み料理や炒め物はつくっても…、なんなんでしょうね。自分でもオカシイと思うのですが。
そんなぼくでも、ちょっと心が引かれる商品を見つけました。宮崎市で昭和54年創業のカレー屋さんが出している、カレーの瓶詰です。お茶わんにちょっとだけごはんが残っちゃったとき、サッとひと口だけ本格的なカレーが楽しめるという逸品です。冷蔵庫に置いておくと便利で、おにぎりの具にしたり、トーストに塗ったり。今までありそうでなかった、その手があったか!という商品です。
開発者の伴好矢さんとは昨年、みやざきフードビジネスセミナーで出会いました。そしてそのとき「これはちょっと新しい商品だと自負しています。でも新しいからこそ、お客さまにオススメするのが難しいんです」と伺いました。たしかにレトルトカレーと単純に比べちゃえば高価だし重いですもんね。「他人がやっていないこと」にチャレンジするのは大変です。
しばらく前、その商品説明のメインコピーは「カレーのつくだ煮」でした。なるほど「つくだ煮」なら、ひと口余ったごはんにも、おにぎりにも使えるわけで、新しい商品の使い方を伝えられています。その一方で、どうでしょう。視覚的には黒っぽく、味覚的には甘じょうゆっぽく感じちゃうのは個人的な感覚でしょうか?
伴さんも試行錯誤を重ねていらっしゃいますが、もしかするともっと有効なコピーがあるかもしれません。

コンセプト=サーチライト
一方「カレーのつくだ煮」を、直接お客さまに語りかける「コピー」ではなく、内輪で進むべき方向を共有する「コンセプト」として活用することもできそうです。コンセプトとは「サーチライト」なので、この場合でいえば「カレー」を「つくだ煮みたいな」という目線で考え直そうということ。そうすると「ひと口ごはん」や「おにぎりの具」だけでなく、「つくだ煮」のあらゆる特徴が新しいカレーを考える切り口になります。
たとえばつくだ煮って、使用する食材違いでいろいろなバリエーションになります。とするならこの瓶詰も、「チキン」「ポーク」「エビ」「根菜」といった展開を考えることが、つくだ煮みたいなやり方なのかもしれません。
あるいはつくだ煮って、特に贈答用のときは上品なビニールパックの個包装が多いです。「なぜ瓶詰なんだっけ?」と検討することもつくだ煮視点のひとつでしょう。
それだけでなく「つくだ煮の老舗感ってどこで表現してるのかな?」「黒く照りがある方が旨そうに見えるかな?」など、新しい商品をブラッシュアップする数多くの視点を与えてくれるのがコンセプトです。
もちろん時として「内輪のサーチライト」として開発した言葉が、まんま「お客さまに説明するときに有効な言葉」になることがあります。とはいえコピーとコンセプトは本来の役割が違うので、きちんと意識して使い分けなければなりません。
そんな能書きはともかく、カレーショップばんの「たべるカレー」は一見の価値ありです。えっ?「『たべるカレー』というネーミングの意味が分かりません。『食べるラー油』を意識しているのでしょうが…」ですって??

たべるカレー商品カット
つべこべ言わないで(笑)、お取り寄せはコチラから。
どうぞ、召し上がれ!