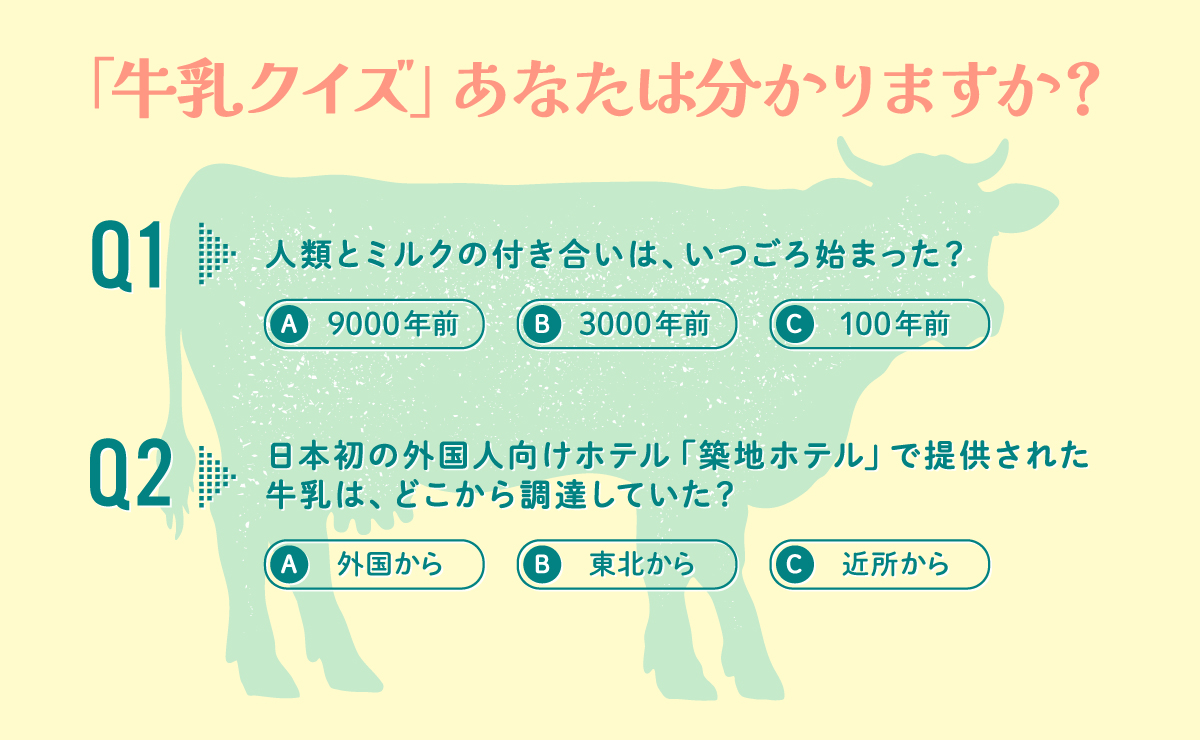さて、皆さん。ここまで読んでいかがでしょう? アートディレクターの下村雄飛さんによれば、今年のカンヌでは全28カテゴリー中、18個のグランプリが難民や差別など「社会課題」に取り組んだものだったそうです。つまり広告業界にとって「社会課題の解決」は身近なテーマのはずですが、その割にはわが業界と公共政策学で、ずいぶんプロセスに差があると思いませんか?
実はこの本の著者、秋吉さんは大学のゼミ仲間。出版祝いと称して夜の街に呼び出し、「なぜ、こんなにアプローチが違うんだろう?」と率直な疑問をぶつけてみました。
いろいろ丁寧に答えてくれた中で印象に残っていることのひとつは、学問としての成り立ち。公共政策学はそもそも「科学的に、客観的に分析をすれば、正しい政策を実施できる」という理念からスタートしたそうです。さすがに今では「究極的には自動的に政策をつくることができる」なんて考える人は学界でも少数派なようですが、それでもなお「合理的に政策決定をしたい」考える人は少なくないのでしょう。理性では説明しきれない人間のコミュニケーションを扱い、感性を大切にする広告業界とは根本的な考え方が違うのかもしれません。
一方で、かつて公共政策学の関心は「省庁や国会での政策決定」にあったそうですが、近年はそれ以前に望ましくない状態をどのような問題としてとらえるか、専門用語でいう「フレーミング」に注目が集まっている、という指摘もありました。たとえば少子化問題は「子どもが生まれない問題」なのか、「高齢者の割合が増える問題」なのか、「人口が減少する問題」なのか、「女性の社会進出が進まない問題」なのか。どのような枠組みでとらえるかによって、対応策も変わってくるという視点です。
これなどは、まさに広告業界で言う「課題」設定の難しさ。「深い人間理解」と大いに関係するポイントです。公共政策学がいくつもの分野を統合する「学際的」な学問を目指しているにもかかわらず、いままでは政治学者と行政学者が中心で、まだまだ経営学やデザイン、広告コミュニケーションの知見を活用できていないのかもしれません。その分、発展の余地も大きいということでしょう。

右が秋吉先生。左は同じくゼミ仲間の日大、手塚広一郎先生。
…などなど。谷中生姜のリゾットや火入れが絶妙な肉類を肴にワインをがぶがぶいってしまったので、途中から細かいことをよく覚えていません。ともあれ「広告の常識」とは明らかに違うアプローチが新鮮なので『入門 公共政策学』、興味ある方はぜひ。
どうぞ、召し上がれ!