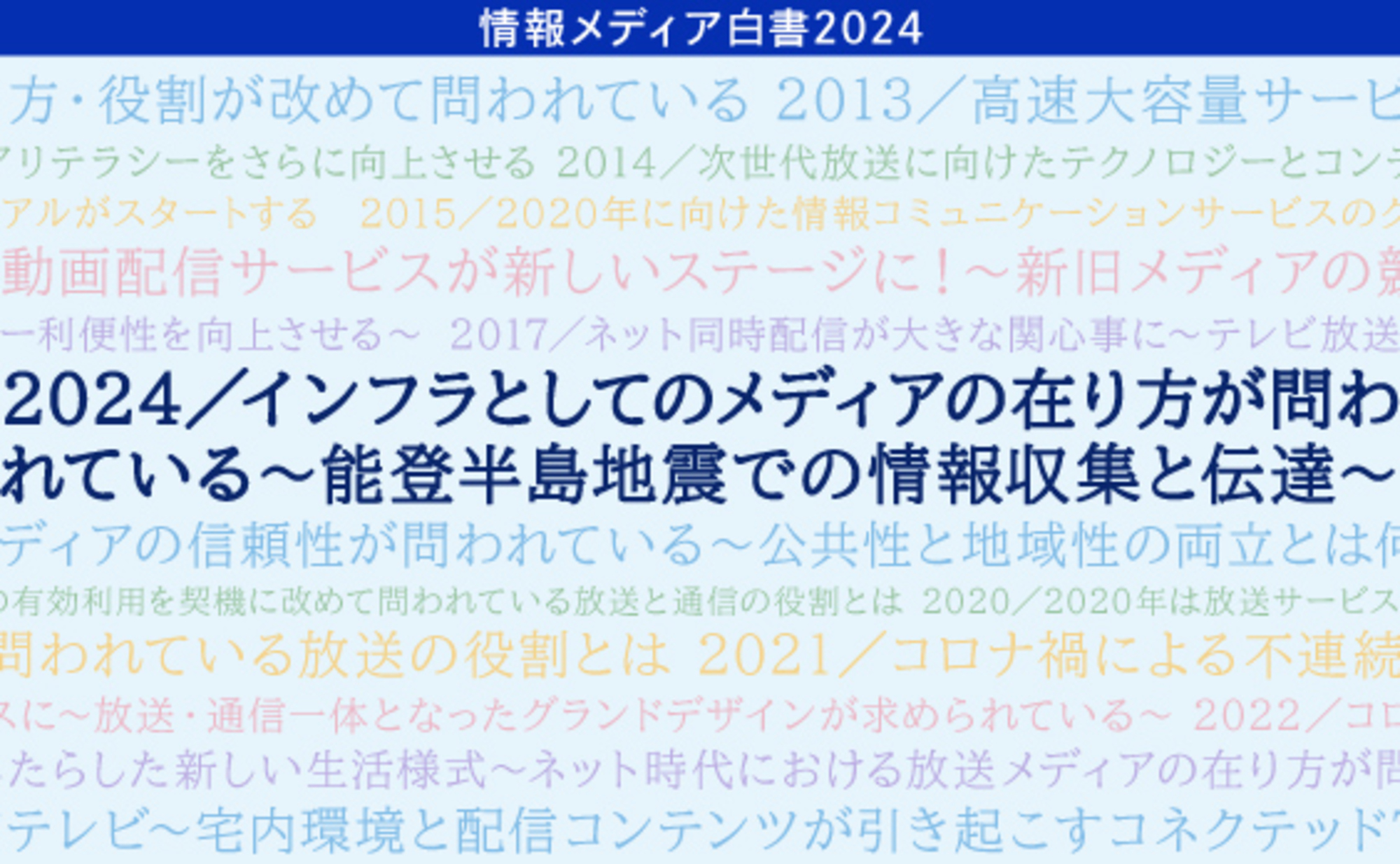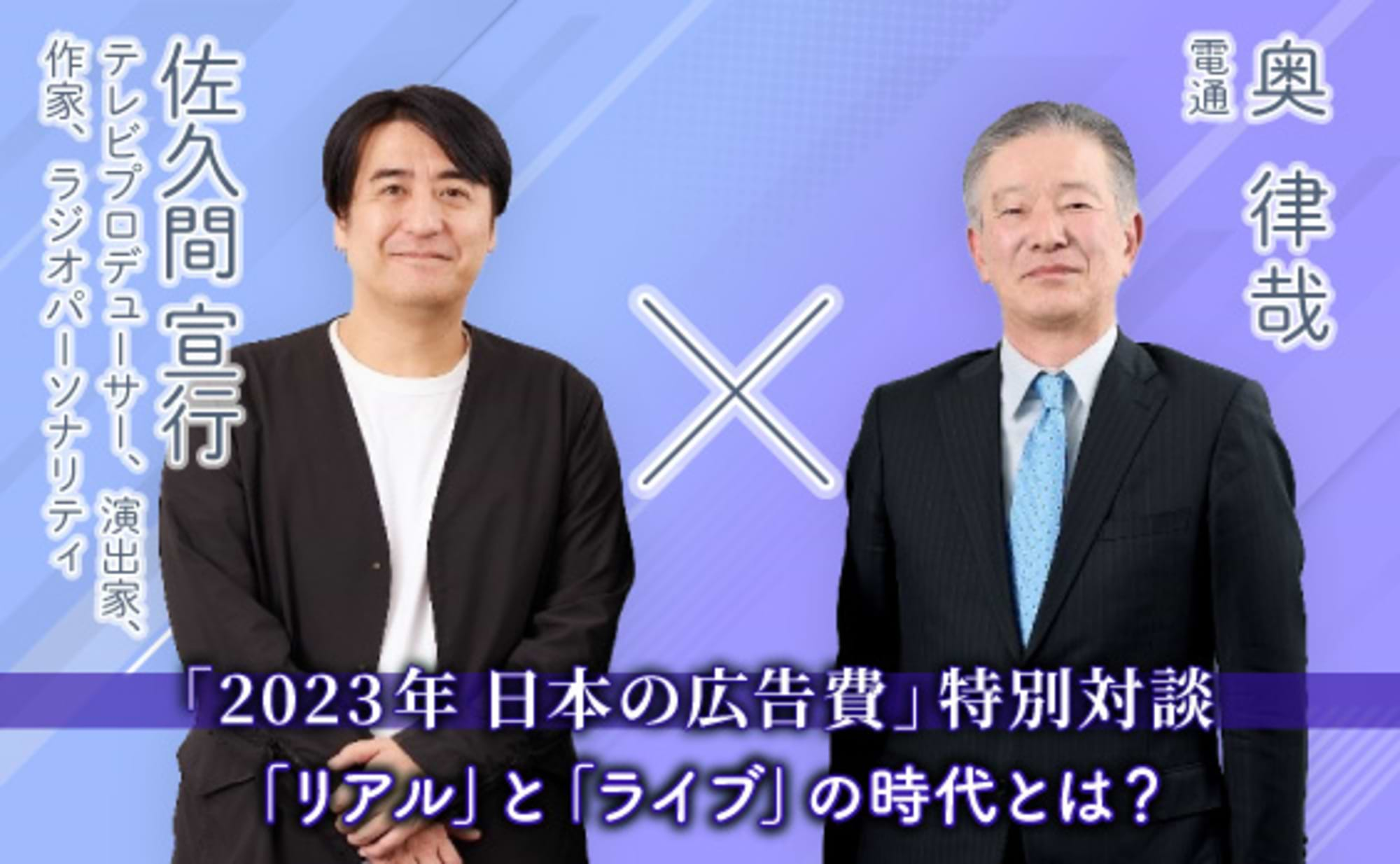新たな広告手法が生まれる中で、広告コミュニケーション・ビジネスはどんな変革を迫られるのか?その特徴と今後の可能性について語り合った。
「枠」を買うのか? 「属性」に焦点を当てるのか?
植村:私は電通ではもともとテレビ出身なんですが、ネットで運用型広告という新手法が出てきて注目されるようになりました。ネット業界では、あらかじめ広告が掲載される「枠」を買うことを予約型と言っています。これは4大マスメディアにも当てはまりますよね。
予約型は、メディアに発注した時点で露出が決まる。何月何日の何時何分。あるいはどの面にこの広告は出しますと。それから請求金額も発注時に確定します。それに対して、発注した段階で露出時間も請求金額も決まっていないのが運用型です。いくらで買えたか、あるいは買えなかったか、フタをあけてみないとわからない。掲載費用の上限は決まっていたりしますが、あとは成り行き。これまでの広告にはなかった世界です。
また、メディアの枠や面で買うか、ユーザーの属性などで買うかという観点もあります。4大マスメディアやポータルサイトの予約型広告は、枠や面で買う。対して、ネット広告には、どこの面や枠に出るかわからないけれども、「40代の、東京に住んでる男性ホワイトカラー」といったユーザーのデモグラフィックをもとに広告を掲示する手法がある。
こういった運用型広告には、広告の機能として2つ大きな問題があります。ひとつは、計画が立てられないこと。たとえば、新製品の発売に合わせて、指定した日に大々的に露出をはかるということができない。だから、キャンペーンなんかには使いにくいと思います。これは、材料の調達や流通対策とか、年間の事業計画にも関わってくる問題ですね。
もうひとつは、先ほどの「属性」をベースにして広告売買をすることからくる問題。確かに「東京在住、40代のホワイトカラー」と属性を絞って訴求することはできますが、でも同じ人間でも、月曜の朝に経済面を見ているときの気分、金曜の夕方に新聞の映画面を見ているときの気分、土曜の昼間に育児をしているときの気分、それぞれまったく違う。それを同じ人間だからと、月曜の朝の企業欄にベビーカーの広告を出してもしょうがない。ずっと4大マスメディアがやってきた、番組や紙面を見る人の嗜好に合わせた広告が打てないわけです。
奥:ネットの世界でも、属性はあまり関係ないサイトはありますよね。
植村:レシピサイトなどはその典型ですね。レシピサイトを見に来る人は、年齢も性別も居住地も関係ない。とにかく料理をしたいという人。だから、調味料の広告をポンと出せばなんら問題ない。人にターゲティングするのではなくて、そのコンテンツやメディアが醸し出す雰囲気に広告メッセージをマッチングすればいいわけです。ですから、コンテンツやコンタクトポイントの価値をまったく無視して、人にターゲティングすればいいという運用型の考え方は、決してすべてに当てはまるわけでないということですね。
予約型と運用型のいいとこ取り? 事前承認運用型という考え方
奥:メディアの設計のときには、4つの要素が重要だといわれます。すなわち、「気分」と「シーン」と「ロケーション」と「タイム」。気分というのは広告の受け手がハイテンションのときか、少し落ち込み気味か。シーンはまわりの状況。自分ではなく、まわりの雰囲気が盛り上がっているのか、落ち着いているのかといったこと。ロケーション(場所)とタイム(時間)は説明するまでもないですね。
この4つの要素は、昔から言われていることですが、今も十分に言い得ていることですね。これらをコントロールできるのが、まさにマスメディアだと思います。そのマスメディアにも運用型のメリットを持ち込む発想はありだと思うんです。たとえば、テレビ広告での枠に入れる素材を、A/B/C/Dと4パターン用意しておいて、天候とかその日の変動要因で直前差し替えするという方法はある。デジタルなら、差し替え自体はさほど難しいことではありません。素材考査も事前にちゃんとしておく。いわば、事前承認運用型。この手法は、総体としての広告のパワーを高めることにもなると思うんですよね。
植村:他のビジネスでも昔からあったことですね。たとえば野球場だと、予約型でまず年間シートを売って、売れ残ったシートを運用というか当日売りにする。ホテルも事前の予約を取って、当日空いている部屋は売る。結局、枠を売るビジネスは、同じことやってきたわけですよね。
これまでのテレビではまだやっていないけど、予約型と運用型の中間型。付加価値を生みそうな面白い手法ですよね。スポットでも、タイムでもできる。どうしてもネット業界はテクノロジー的な流行りで、片方にワーッと行きがちですが、売る側も買う側も、要はバランスの問題で、両方うまく戦略的に使い分ければいいと思いますね。本当の広告目的、広告心理ってなんだろうということをきちんと見極めたうえで流行に流されず、クライアントのニーズに応じたやり方があるはずです。
奥:先ほど植村さんが言った運用型の問題点に、もうひとつ注意点を加えるとすると「属性」で広告売買をする際、ターゲティングの問題がありますね。ターゲティングが本当にしっかりしていればいいんだけど、意外とターゲットの外側の人が財布のヒモを握っていたりすることが現実には多々あるわけです。例えば、男性向け商品でも、決定権は奥さんが持つ場合もあります。加えて、属性で単純に切れないケースもある。この地区に住んでいて国際的な活躍をしてる層だとか、まったく違う文脈で切るターゲット像もある。そういう応用がどこまできくのかという問題もあるのではないでしょうか。
植村:だから、運用型にするとピンポイントにはできるけれども、いやピンポイントじゃなくて、もっとファジーに、という場合はありますよね。
奥:レーザー照射のようにピシッと当てていくのもいいんだけど、まわりにも決定権をもった人がいる可能性もあるわけだし、やはりバランスの問題ではないでしょうか。
植村:ネットでは、過去のデータを見ているわけですが、たとえば、ある人がクルマのページを過去3週間よく見ていたとしても、もう買っちゃっているかもしれない。過去のデータだけで、単純に未来予測はできません。
奥:新しい広告手法を取り入れるにしても、メディア側も、広告コミュニケーション・ビジネスに関わる人間も、技術だけによらず、もっと知恵を絞っていく必要はありそうですね。