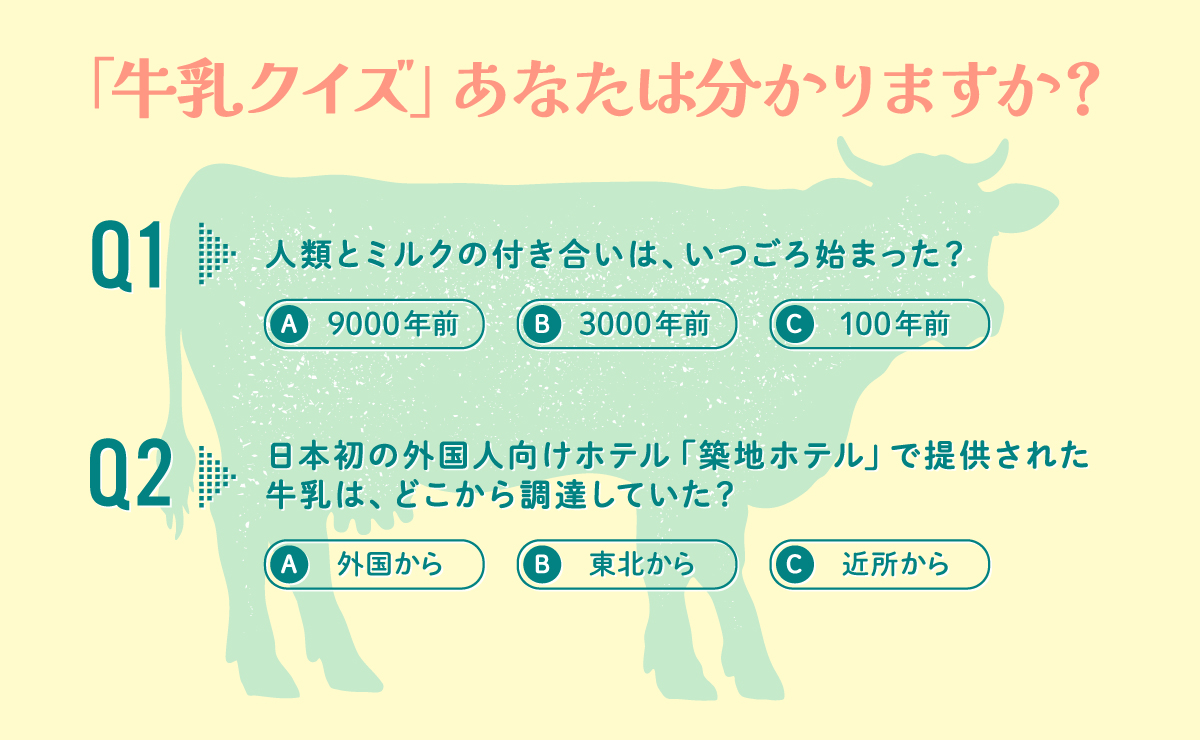小学校から高校までを過ごした横浜市の鉄町は佐藤春夫「田園の憂鬱」の舞台になった場所。中学時代、そのことをきっかけに「秋刀魚の歌」を知りました。
さんま、さんま
そが上に青き蜜柑の酸をしたたらせて
さんまを食ふはその男がふる里のならひなり。
(中略)
さんま、さんま
さんま苦いか塩つぱいか。
そが上に熱き涙をしたたらせて
さんまを食ふはいづこの里のならひぞや。
(佐藤春夫「秋刀魚の歌」から抜粋)
しかし谷崎潤一郎の妻に寄せる思いを詠んだ、この歌。なんともなんとも、当時のぼくはまったく理解できませんでした。
ここで描かれる心象風景はさておき、脂ののった秋刀魚には大根おろしが欠かせません。そして佐藤春夫の故郷、和歌山の習慣だった「青き蜜柑」(すだち的なもの)も、いまや全国的な常識。まさに完璧な組み合わせ。これに熱燗でもあれば、もう言うことなし!です。
ところで広告界の巨人、J・W・ヤングが四半世紀前に看破したように、画期的に思えるアイデアも、結局は「既存の要素の新しい組み合わせ」以外の何ものでもありません。
和菓子職人×前衛芸術家、アスリートの知恵×工場の生産管理、海底×農業
こういった大胆な組み合わせは、常に「アイデア」を生み出す可能性に満ちています。しかし奇抜な組み合わせをしただけでは、「アイデア」にはなりません。なぜなら、それはまだ「課題を解決する新しい視点」になっていないからです。
アイデアをつくる思考プロセスを四つのモードで整理した「ぐるぐる思考」でいえば、こういった無数にある新しい組み合わせを試行錯誤するのは「散らかす」段階です。そこにあるのはまだ単なる「思い付き」。
それから七転八倒、あらゆる可能性を考え尽くして、ようやく手に入る視点。「これなら課題を解決できる」と、ようやく「発見!」されるのがアイデアです。
広告会社がいままで培ってきたノウハウを、広告以外の領域へどんどん転用し、いままでになかったビジネスチャンスをつくる動きに、ぼくは心から賛同します。しかし、もしそれが単に新しい出会いの場をつくるだけなら、それをもって「アイデアのプロデュース」というなら、個人的にはちょっと疑問符を付けたくなります。
「いっちょかみ」という大阪弁は、たぶん広告パーソンに共通する性質を言い当てています。それは「何にでも手を出さないと気が済まない性分の人」を意味するので、J・W・ヤングが言った、クリエーティブな人間は皆、例えばエジプトの埋葬習慣からモダン・アートに至るまで何にでも興味を持ち、あらゆる知識をむさぼり食う傾向があるという話にも通じます。
と同時に「いっちょかみ」には、「ちょっと首を突っ込んでは、すぐ飽きる人」という意味もあります。もし出会いの場をセッティングするだけ、それでうまくいかないと、すぐ飽きちゃうようでは、やっぱり「アイデアづくり」に参加しているとは言えないと思うのです。
ここに広告領域以外でアイデアづくりをする難しさがあります。そこでは、単に首を突っ込むだけではない、主体的な参加が求められます。慣れ親しんだ広告以外の領域で、専門知識もない中、いかに粘り強く関わるか。「いっちょかみ」ではない姿勢こそが必要だと思うのですが、いかがでしょう?
どうぞ、召し上がれ!