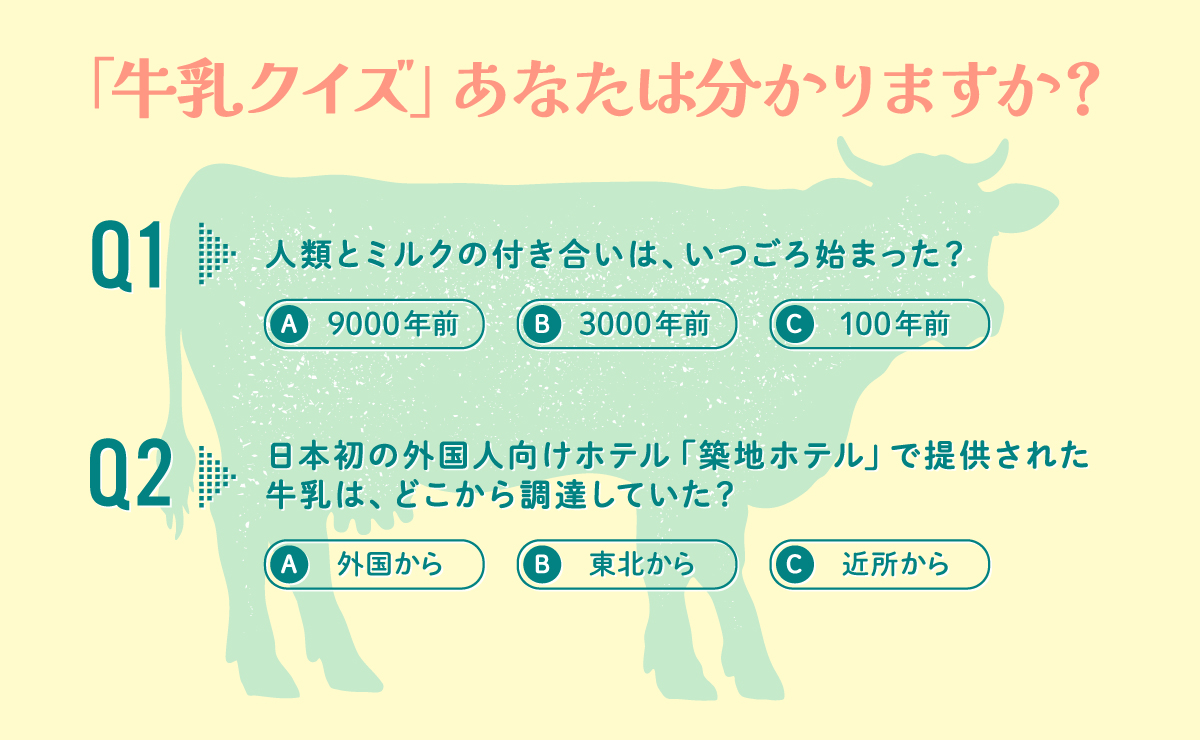ぐるぐる思考はコンセプト(アイデア)づくりの方法論です。感じるモードで材料を集め、散らかすモードでありとあらゆる可能性をリアルに検討し尽くし、発 見!モードで目標・課題と論理的に整合する言葉「コンセプト(アイデア)」を手に入れます。そして今回からお話しする「磨くモード」で具体策をつくるのです。
それはコンセプト(アイデア)で具体策を「磨く」プロセスです。コンセプトとはサーチライトのようなものですが、それによって暗闇に浮かび上がる具 体的なモノ・コトを形にします。広告キャンペーン開発であればTVCM、プロモーション、メディアなど様々な専門家がコンセプト(アイデア)の示す方向性 に従って個々の施策をつくっていきます。
と同時にそれは具体策でコンセプト(アイデア)を「磨く」プロセスでもあります。いった ん 指針となる言葉を手に入れると、それを金科玉条のように絶対不可侵にして突進する人がいます。しかし環境は日々変わるもの。技術的な問題で当初想定したよ うなアウトプットが出来ないこともあるでしょう。そんなときはフレキシブルにコンセプト(アイデア)を見直すことが大切です。
いままでやってきたことをリセットして、コンセプト(アイデア)と具体策を行ったり来たりしながら新しい視点に基づいて全体を再構成するのが「磨くモード」の実際です。
地方の逸品が見つかるお取り寄せサイト「よんななクラブ」の名物企画「あるんだ!勝ち抜き選手権」を15回勝ち抜いて「横綱」の称号を手にした「宇都宮で一番濃いミートソース」は、新しいコンセプト(アイデア)で商品を作り直したよい例です。
オーナーの加藤裕さんによれば、1997年宇都宮に開店した「すぱ屋」は当初「お腹いっぱい」がコンセプト(アイデア)でした。そしてそれを実現するために一人前を乾麺で150g(通常の1.5倍)に、量を食べられるように味付けも上品にしていました。
しかし市内にイタリア料理店が増えてくると単なる大盛りでは限界がありました。「このメニューなら『すぱ屋』でなくてもよいのではないか?」という悩みが大きくなっていったのです。そこで加藤さんは関東一円で100軒以上のパスタ屋さんを食べ歩き「他の店ではやらないことをやろう」「自分が食べたいメニューをとがらせよう」という覚悟を決めました。
多くの店をまわって感じたのは「もう一回食べたくなるのは美味しいものより印象に残るもの」ということ。そこで新しいコンセプト(アイデア)を「一口目にガツンと来て、二日後に思い出す味」と設定し、すべてをゼロベースで再構成していきました。実際、それまで使っていたミートソースの改良では目指しているような商品をつくれないと判断。いままでのレシピを捨てて、一番最初にコンセプト(アイデア)に相応しい「見た目の色」を定め、そこから数え切れない試行錯誤をしながらソースの味を調えていったそうです。もちろん麺もオリジナル。コンセプト(アイデア)に従って製麺工場の社長さんと試作を重ねた自慢の太麺です。
結果出来上がった商品はホームページで「決して万人向けではない」と自ら認めちゃうほど特徴的。もちもちの太麺にこってり甘いソースがからまって、どこかで食べたような初めてのような、給食のソフト麺が進化した感じというか、なんとも懐かしく新しい味わいです。
全体をゼロベースで構成し直すのは容易でありません。とはいえちょっとでも「いままで通りでいいだろう」という甘えが出ると新しいコンセプト(アイデア)の切れ味はすっかり失われてしまいます。「宇都宮で一番濃いミートソース」はいままでのミートソースを完全に捨てた点が見事です。そこには妥協を許さないプロフェッショナルの誇りがあります。しかも最初のインパクトをマックスにする「見た目」からソースをつくる大胆さがユニークな商品に結実したのでしょう。
さて、次回も引き続き磨くモードの難しさについてお話しします。特に経営学の世界で「死の谷(Valley of Death)」と呼ばれるものについて触れようと思います。
どうぞ召し上がれ!