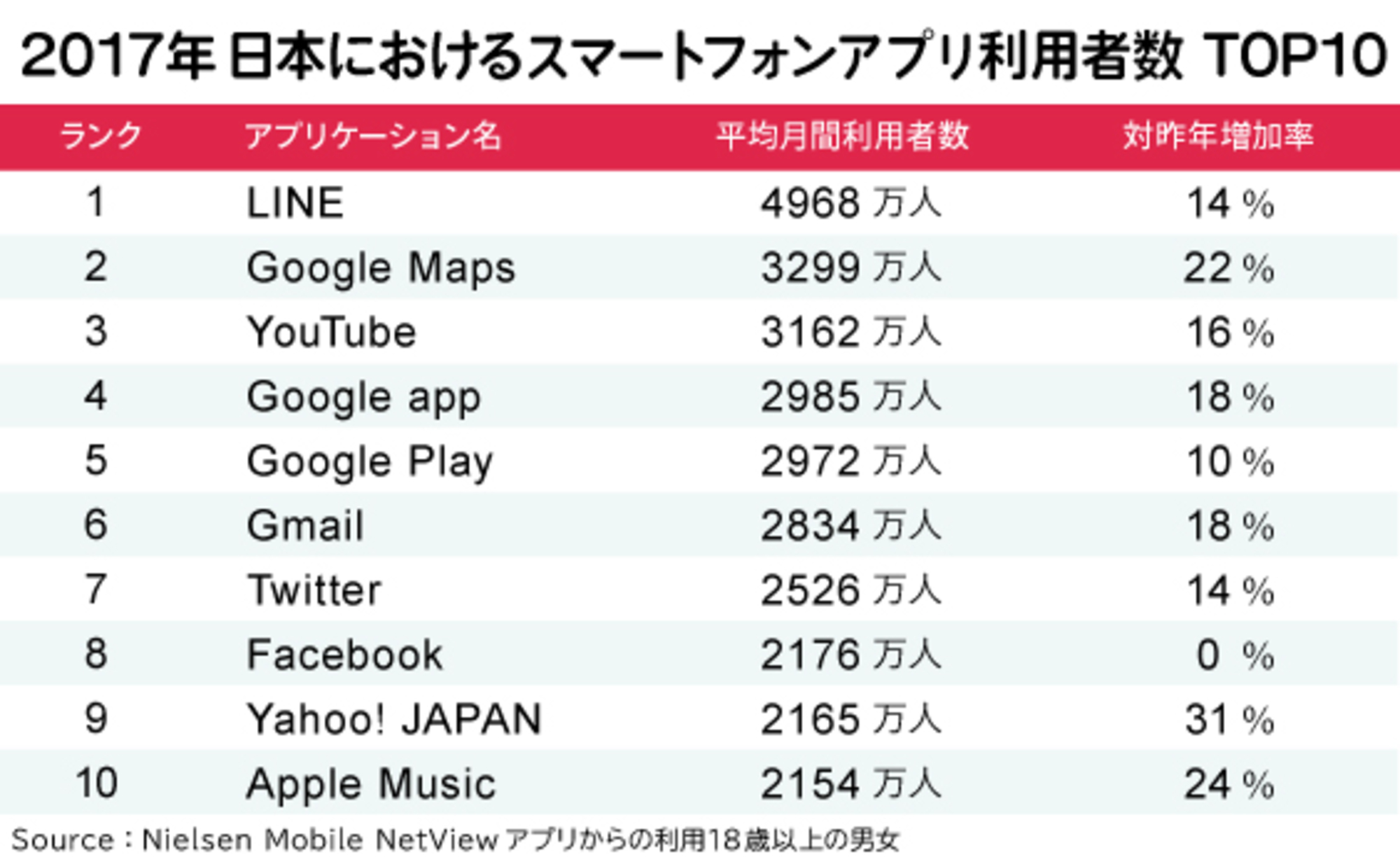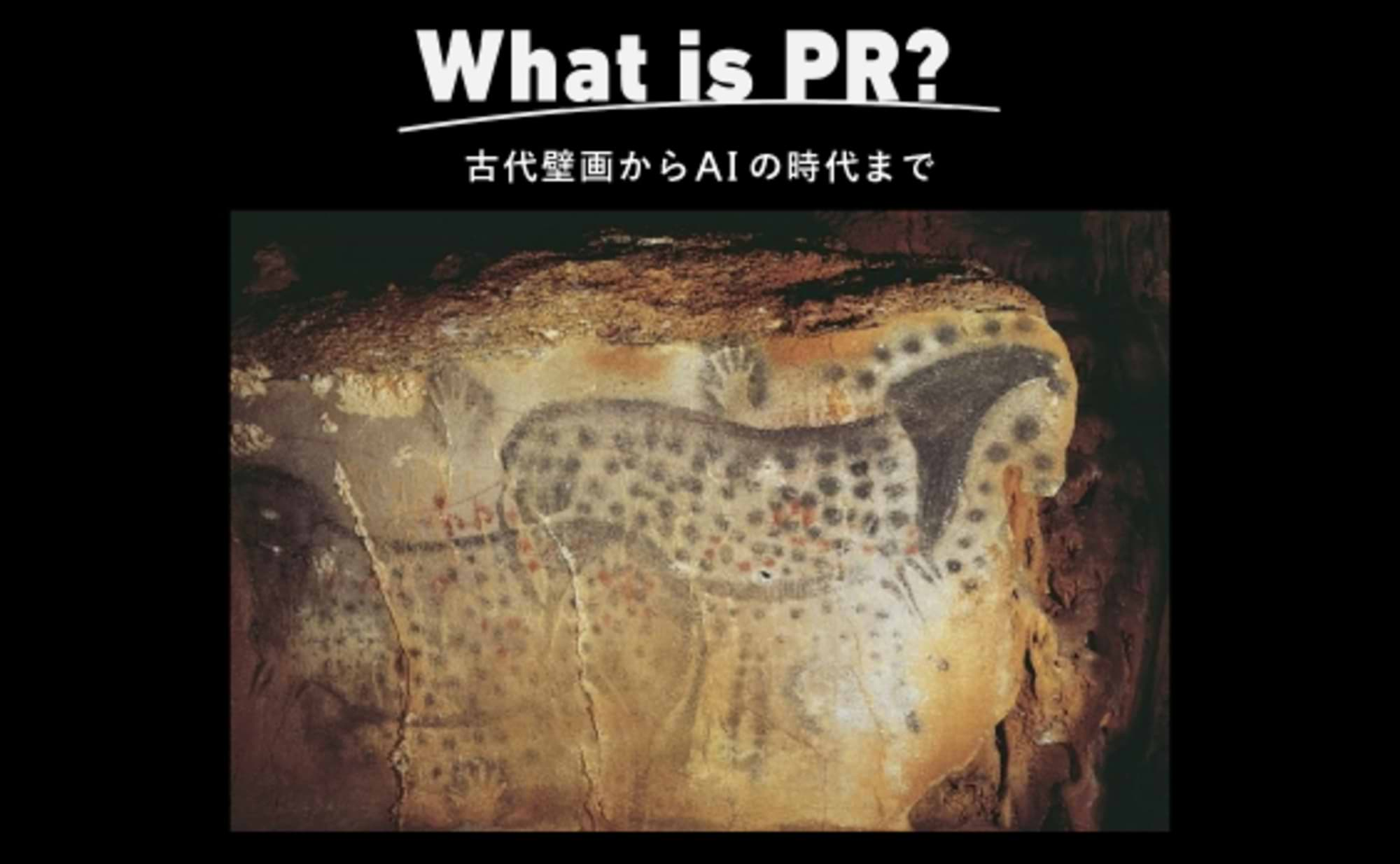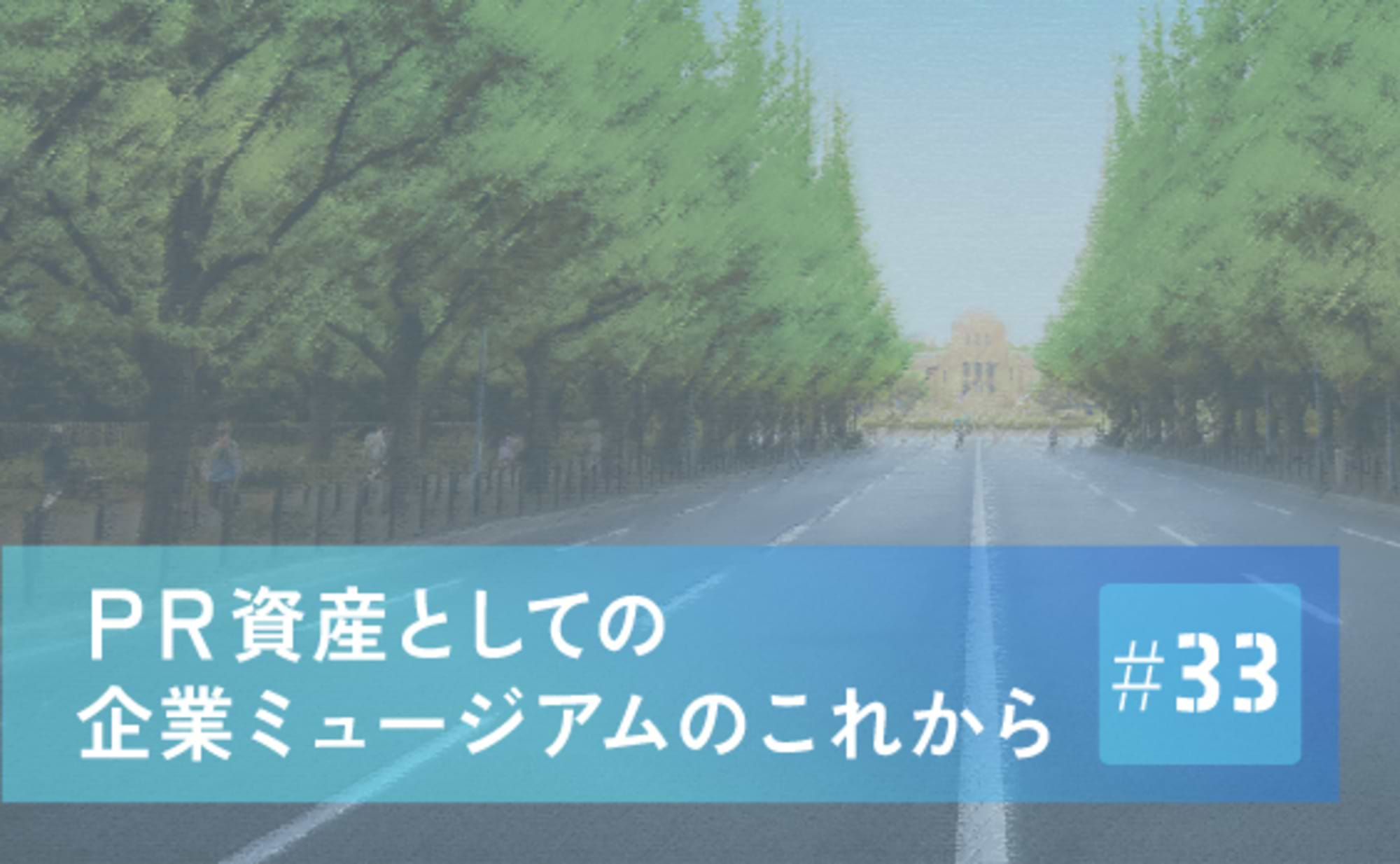公開日: 2018/05/10
ポイント5: “The Art of Apology” 日本の謝罪会見とお辞儀
この記事は参考になりましたか?
著者

藤井 京子
株式会社 電通PRコンサルティング
エグゼクティブオフィス広報部/国際教養大学大学院客員准教授
国内外の企業、政府、自治体のパブリックリレーションズをサポート。現在は同社の広報を担当。2015年国際PR協会ゴールデンワールドアワードを受賞。編著書『成功17事例で学ぶ 自治体PR戦略』(時事通信社)、『Communicating: A Guide to PR in Japan』(Wiley)、「企業ミュージアムへようこそ 上下巻」(時事通信)など。日本PR協会認定PRプランナー。 2024年から国際教養大学大学院客員准教授(Graduate School of Global Communication and Language)。
連載