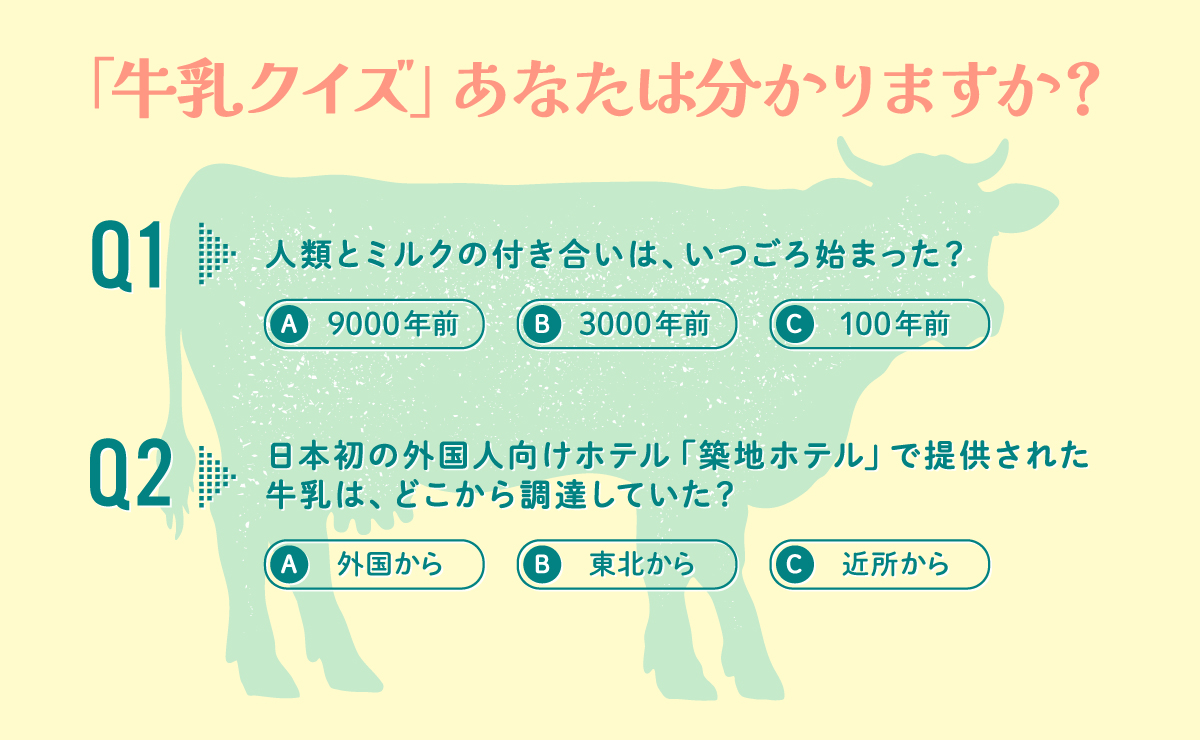今月11日は母の日。以前にも書きましたが、昭和9年生まれのぼくの母は息子と違ってグローバル。幼稚園はスイスのジュネーブだったそうで、昔から「あのとき食べたポレンタが忘れられないわ」なんてことを言っていました。最近でこそたまに見かけるようになりましたが、ポレンタとは粗挽きのトウモロコシ粉を煮てつくるイタリア料理。母は鶏のスープで炊いてから焼き目をつけ、肉料理の付け合わせとして食卓に出してくれます。

さて。拙著『〈アイデア〉の教科書』でご紹介したコンセプト(アイデア)をつくる方法論「ぐるぐる思考」は広告会社に伝わるユニークな思考プロセスをまとめたものですが、モデル化するに当たっては広告会社の経験と経営学の知見がベースとなりました。そこで今回は「ぐるぐるの母」と称し、広告におけるアイデアづくりの方法論についてお話ししましょう。
かつてアメリカ広告代理業協会の会長などを務めたジェームズ・w・ヤングが書いた世界的ベストセラーに『アイデアのつくり方』(1940)があります。ここでは「アイデアの作られる全過程ないし方法」が紹介されています。
第一 資料集め---諸君の当面の課題のための資料と一般的知識の貯蔵を絶えず豊富にすることから生まれる資料と。
第二 諸君の心の中でこれらの資料に手を加えること。
第三 孵化段階。そこでは諸君は意識の外で何かが自分で組み合わせの仕事をするのにまかせる。
第四 アイデアの実際上の誕生。〈ユーレカ!分かった!みつけた!〉という段階。そして
第五 現実の有用性に合致させるために最終的にアイデアを具体化し、展開させる段階。
ヤング自身が「理解を深めるため」の文献として挙げていますが、このベースとなったのはイギリスの社会学者グラハム・ワラスが『思考の技術』(1926)で紹介した「①準備(Preparation)→②あたため(Incubation)→③閃き(Illumination)→④検証(Verification)」という「四段階説」です。そしてこれは100年近くたったいまでも広告業界における定番的アプローチです。

ぐるぐる思考の「①感じる(Feel)→散らかす(Scatter)→③発見!(Eureka!)→④磨く(Polish)」という四つのモードもそれぞれ四段階説に対応し、その実際をより詳細に説明しようとしたものです。
たとえばヤングはアイデアを手に入れる瞬間(=③閃き)を突然訪れる神秘的な経験として紹介していますが、ぐるぐる思考ではその本質を「整理」と考えています。(参照:第17回)また、ぐるぐる思考では「課題はアイデアと同時に発見される」としている点も特徴的です。
あるいはアイデアの材料について。ヤングは西洋的な知識観に基づいて「知識」と「資料」という言葉をほぼ同義に使っていますが、ぐるぐる思考では言語化(≒資料化)できない職人の技や経験、勘といった「身体化された知識」までをもアイデアの貴重な材料と考えます。(参照:第11回/13回)
いくつかの違いはありますが、既存知識を組み合わせて新しい視点をつくる大きな骨組みは同じです。ぐるぐる思考は四段階説を母として、この世に誕生しました。
 |
ぼくのポレンタ。何かが違う・・・
|
今年のお正月には皇居一周を散歩するほど元気だった母がクモ膜下出血で倒れたのは1月下旬のこと。こういうのって突然起こるんですね。その後、4回の手術を経て最近ようやく明るい兆しが見えてきました。どうもぼくが作るポレンタはひと味足りません。早く元気になって昭和ヒトケタ帰国子女の腕前を披露してくださいな。
次回は「ぐるぐるの父」についてです。
どうぞ召し上がれ!