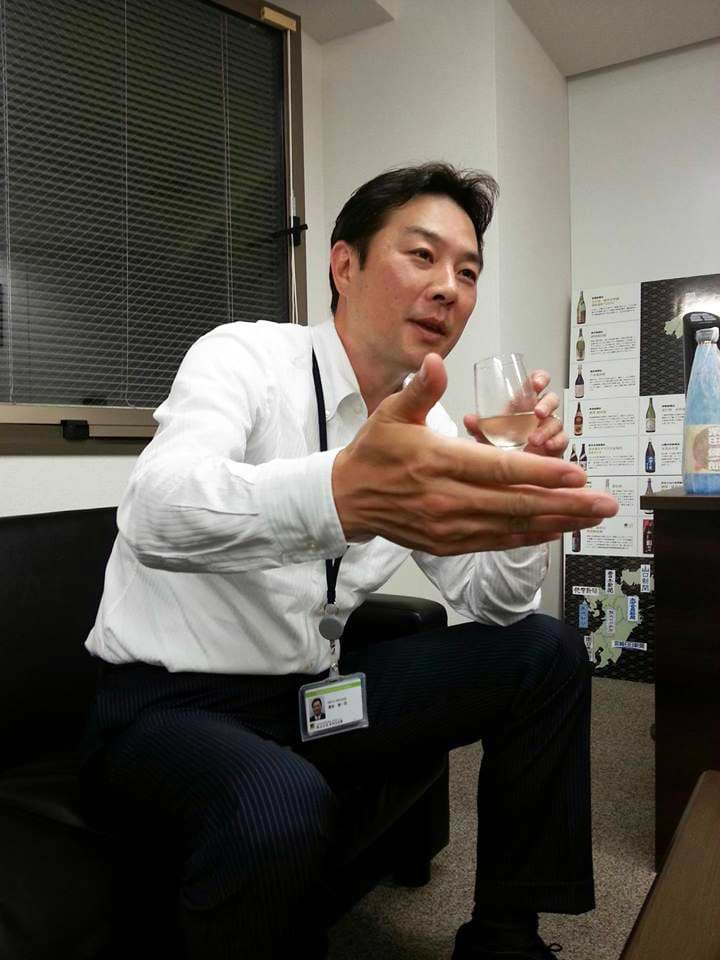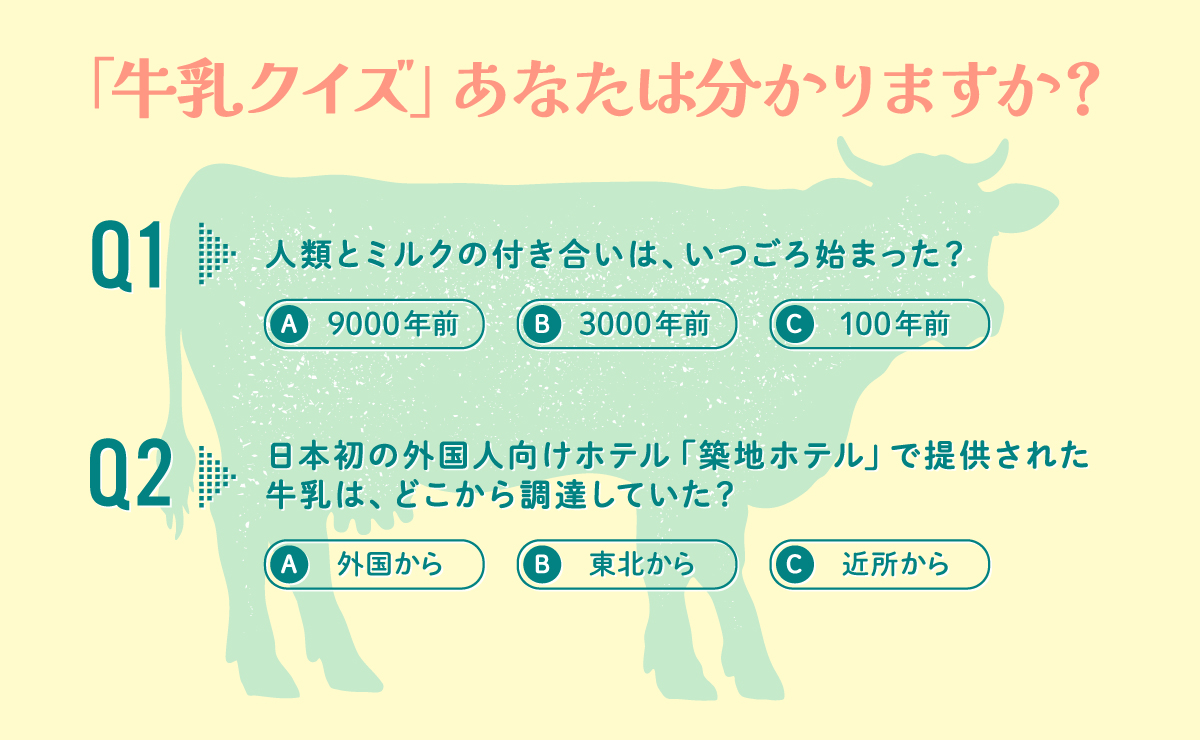昭和40年代末、こどもだったぼくの好物は「タリアテッレ」でした。横浜元町の入り口からアイスクリーム屋、巨大な椅子が置いてある家具屋を抜けて、階段を上った2階にあったイタリアンレストラン「MIKI※1」 でよく食べました。マッシュルーム入りの白いクリームソースにパセリが散らしてある平打ちのパスタが美味しくて、美味しくて。呪文のようなメニュー名、一緒に食べたライスコロッケ、やさしい女主人と薄暗い店内。「好きな食べ物はタリアテッレ」なんて自分でも生意気なガキだったと思いますが、5歳の記憶はいまだに鮮明です。

缶づめマッシュルームを使って自分で再現も…。
う~ん、違うなぁ。
わが家は家庭料理からして変わっていました。昭和9年生まれの母がよくつくったのは「ムサカ」。正式なギリシャ料理のように羊肉ではありませんでしたが、茄子とホワイトソース、ミートソースを層状に重ね合わせたグラタンです。これをおかずに白いご飯を食べていましたが、学校の友達にこの「ムサカ」が通じないのです。もうちょっと普通の料理をつくってくれと母にお願いしても、祖父の仕事で幼稚園はスイス、大学はアメリカだった帰国子女の理解は得られず、お弁当のサンドイッチはピーナッツバターにジャムとバナナ。デザートはトライフル。不思議な食卓が続いたのでした。

久々に母につくってもらった、わが家のムサカ
昔はすいぶん文句を言いましたが、いまではこの経験に感謝しています。ぼくは食関連の仕事が得意だと(少なくとも自分では)思っているのですが、それはきっとこどもの頃から蓄積した引き出しのお陰です。
電通の大先輩、杉山恒太郎さんが「アイディアは思い出すもの」「きみのアイディアは、きみだから思いついたものなんだ※2」と仰っている通り、多様な経験はアイデアづくりの強い味方です。
アイデアの材料となるのは特殊知識(製品とターゲットに関する知識)と一般知識(人生経験すべて)です。特殊知識はその場に応じて吸収することができますが、一般知識は一朝一夕にはどうしようもありません。
広告会社に伝わるユニークな思考プロセスをモデル化した「ぐるぐる思考※3」 は「目標に向けて課題を解決する新しい視点(=アイデア)」をつくる方法論です。そして、その第1段階「感じるモード」の目的はこの2種類の知識を準備することにあります。
その後「散らかすモード」でありとあらゆる可能性を考え尽くし、「発見!モード」でアイデアが手に入り、「磨くモード」で新しい視点に基づいて全体が再構築されて。具体策が世に出るのと同時に新たな知識の吸収、つまりもう一度「感じるモード」が始まって。4つのモードが連続するスパイラルとして発生するのが「ぐるぐる思考」なのですが…これではよくわからないですよね。

ともあれ今回からしばらくは、このアイデアづくりの方法論についてお話しします。ちょっとハードな内容なので、ときにのど越しが悪くなるかもしれませんが、できるだけ気楽に美味しく読んでいただけるようにしたいと思っています。
どうぞ召し上がれ!
※1 MIKIは残念ながらもうずいぶん・・・たぶん30年くらい前に閉店。
※2 杉山恒太郎『クリエイティブマインド』インプレスジャパン、2011年より。
※3 拙著『〈アイデア〉の教科書』に詳述。野中郁次郎先生のSECIをベースに個人によるアイデア発想モデルとして開発した。