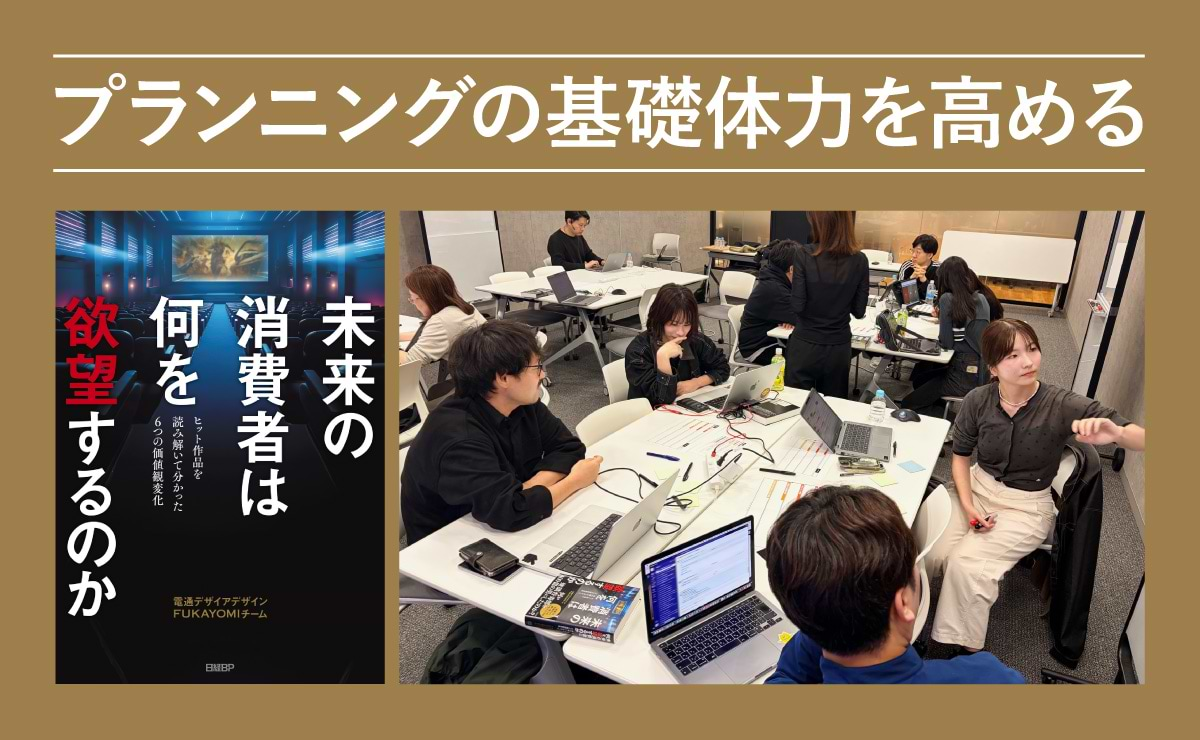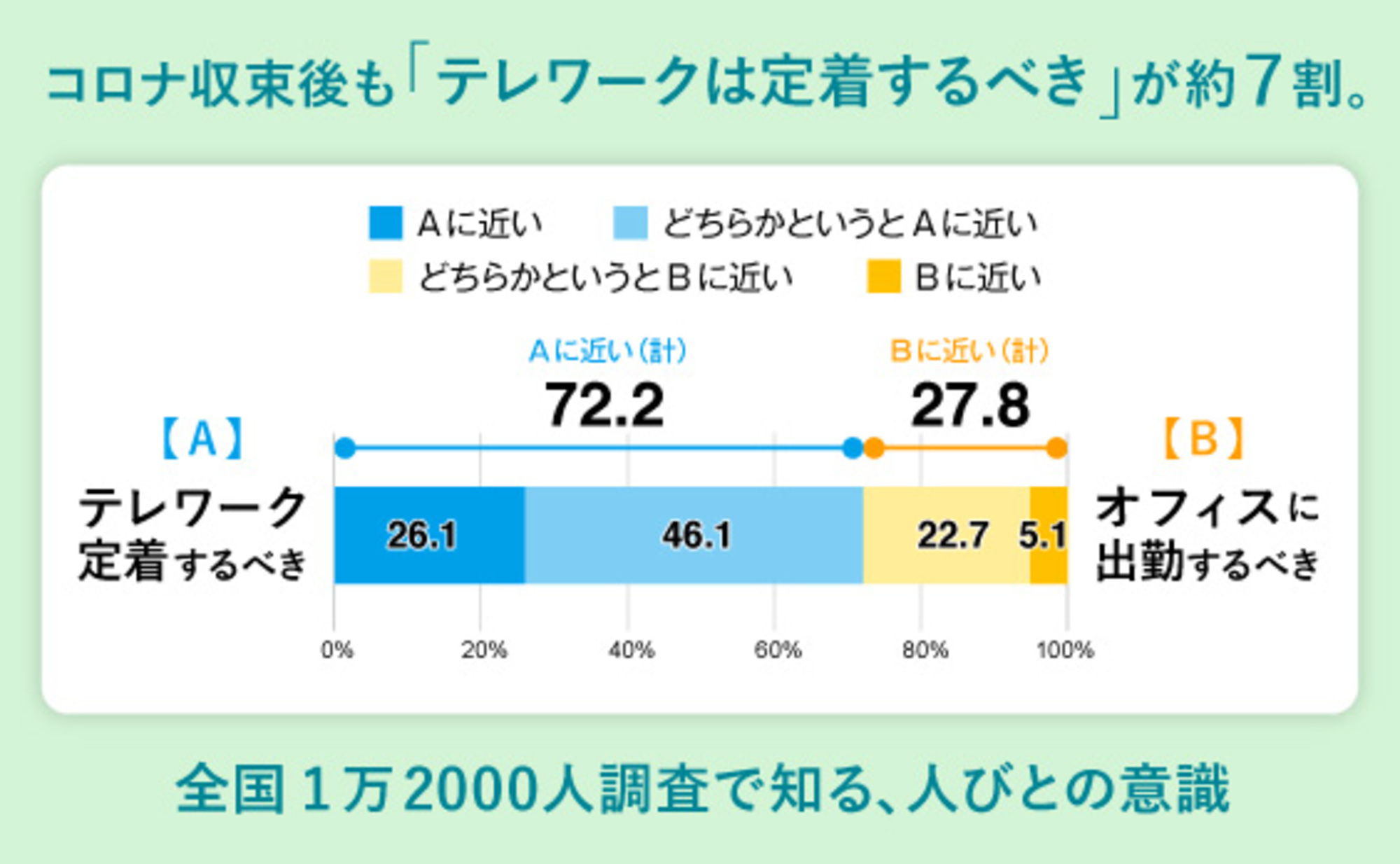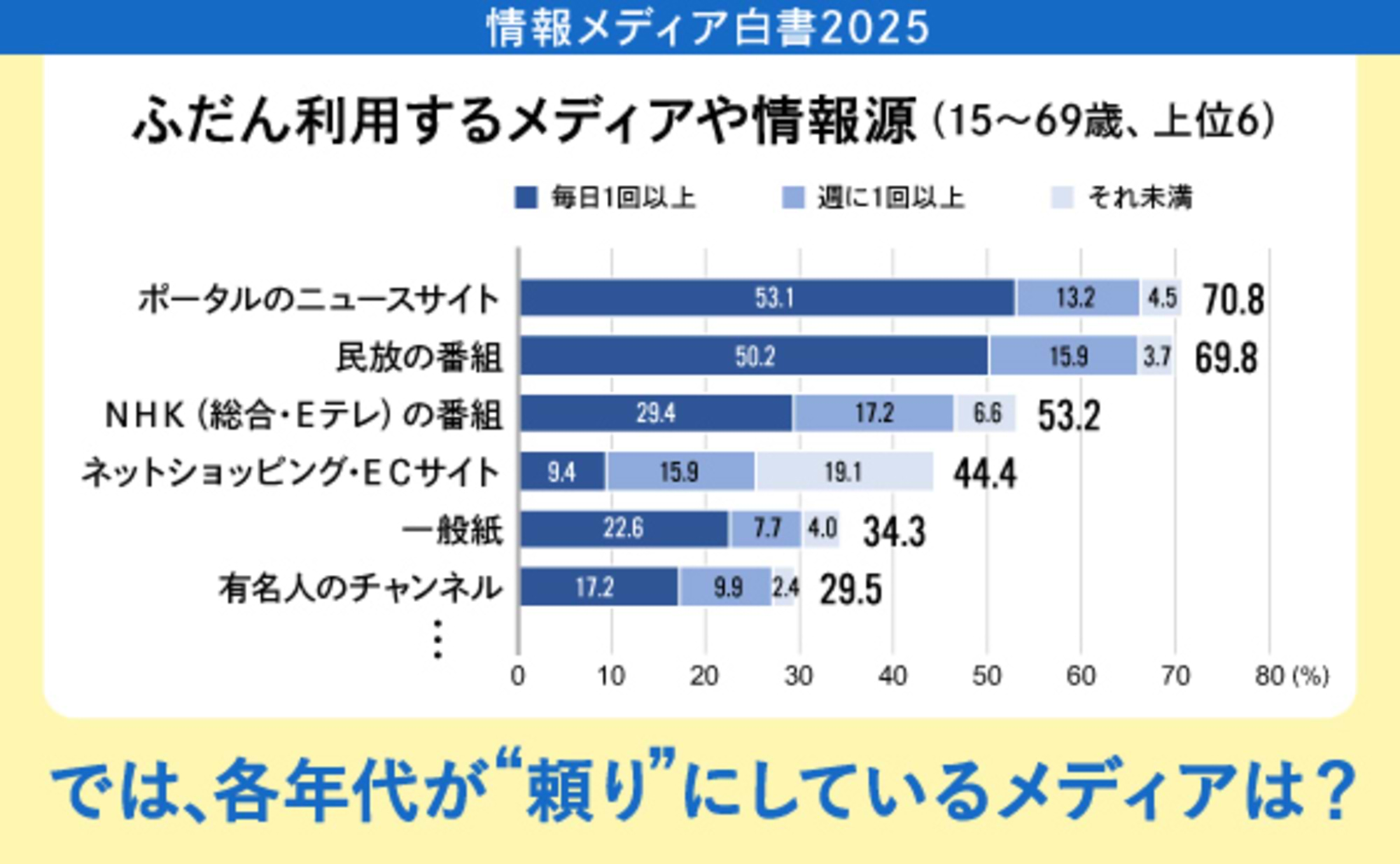【本ガイドラインの使い方】
1.キャンペーンのマーケティング目的、目標とする態度変容に応じて、合致する「特徴・特技」を持つCGを選ぶ
2.そのCGに属する組み合わせの中から、動画メディアと広告表現タイプを選ぶ
以上です。
四つのコンビネーショングループ詳細
CG1「需要生成型」
「認知関心」から「購入検討」まで親和性が高いグル―プです。
企業/ブランドへの関心や好感を高め、検索など“購買検討行為”に導く。新商品・新サービスのキャンペーンで特に重要なCGです。生活者との関係構築の最初の一歩を踏み出す、切り込み隊長的な役割を期待できます。
注目したいのは「テレビ(リアルタイム視聴)」というメディアに対し、「商品特徴型」「アイコン型」「コンテンツセントラル型の一部」「企業/精神型」など幅広いタイプの広告表現タイプの組み合わせがCG1に含まれる点です。「さまざまな広告表現でブランドを認知や購入に結び付けられる」という、コミュニケーション戦略への柔軟性もテレビの利点といえそうです。
居間などでの快適な視聴環境、画面との距離感から生じる心の余裕、定着された視聴習慣が、広告へのオープンマインドな受容を促しているのかもしれません。デジタル広告でターゲティングの高度化が進む中、ノンターゲティングのテレビCMが持つこのような性質はあらためて注目したいと思います。
また、「YouTube」上では「商品特徴型」「アイコン型」が、「Facebook」「Twitter」「新聞のデジタル版」といったメディア上では「商品特徴型の一部」という組み合わせがCG1に属します。
CG2「購買距離短縮型」
名前の通り「購入検討」系の態度変容に特に強みがあるグループです。「認知関心」系にも強いです。
一度関心を持ったブランドへの購買欲を高め、検索やトライアルといった検討行為に導く。購買というゴールまでの距離を短縮させるイメージです。
「雑誌のデジタル版・サイト」「動画配信系サービス」など、やや利用者がセグメント化されているメディア上で、「商品特長型」「アイコン型」といった広告表現との組み合わせがCG2には多く見られます。
つまり、ある程度能動的なメディア接触においては、同じ広告表現でも「より自分ゴト化された商品情報」として扱われる傾向があると考えられます。4マスでいえば雑誌広告に近い機能を持ったグループではないでしょうか。
CG3「商品価値共有型」
「BUZZ拡散」「FAN化」といった態度変容に親和性が特に高いグループです。「購入検討」系にもそこそこの親和性があります。
「広告の拡散」「その企業ブランドを好きになってもらう」など、ブランド価値を生活者の心の中に徐々に浸透させる効果が期待できます。
このグループでは「Facebook」「Twitter」といったSNS、「新聞のデジタル版・サイト」「Yahoo!ニュース」といったテキストニュースメディア上で、特に「第三者推奨型」「コンテンツセントラル型」という広告表現との組み合わせが多く見られます。SNS、ニュースサイトといった一種の“公共空間”で広告が受容された時、商品への興味に加えて、社会的共感のようなものが生まれやすいのでしょうか。
そこに載せる広告も、「第三者推奨型」や「コンテンツセントラル型」といった、「商品の直接的訴求ではないタイプ」の広告表現がより多く符合しています。
CG4「エンゲージ形成型」
CG1とはちょうど裏返しで、「BUZZ拡散」「FAN化」系の態度変容にだけ特に優れたグループです。
認知や購入意向ではなく、「広告を拡散させる」「キャンペーン参加」「ブランドへの支持表明」など、顧客の自主的な関与を高め、いわば顧客を味方にしていく効果を後押しします。
「顧客の優良化によって、LTV(ライフタイムバリュー)を高めていきたい」といった今日的なマーケティング課題に対応しているといえましょう。
SNS「Instagram」が、多くの広告表現タイプとの組み合わせでこのCGに所属しており、BUZZ拡散、FAN化の両方の態度変容で親和性が高いのが印象的です。マーケティング的な利害に左右されない、個人の感性の発信共有の場といったメディアの印象が奏功していると思われます。例え広告であっても、心の琴線に触れた場合は気に入った投稿と同様に受容され、共感を形成していく効果があるのではないでしょうか。
また「GYAO!」「AbemaTV」「ニコニコ動画」といった動画系メディアと、「コンテンツセントラル型」との組み合わせの多くがCG4に属します。
BUZZ拡散、FAN化は、生活者にある種の“自己投企”を要請する、本来はハードルの高い態度変容です。それに対応するCG4は希少価値があり、うまく活用するべきでしょう。
コンビネーショングループで「メディア戦略」と「コミュニケーション戦略」を融合!
最後にもう一つ。今回抽出したCGを活用することで、分断されがちな「コミュニケーション戦略」と「メディア戦略」の連携もできるのではないかと考えています。
「見込み顧客→トライアルユーザー→カスタマー→ファン」と徐々に顧客を優良化していくファネルを想定した場合、各CGは図6のように対応します。
図6 ファネルの各段階に対応するコンビネーショングループ
それぞれのフェーズで「メディアと広告表現の組み合わせをどうすべきか?」という問いにも、示唆を与えることができるでしょう。
“料理と皿”をめぐる差異の視点を得る
料理と皿に例えながら、調査結果に基づき動画広告について私の考えを述べました。
デジタルメディアの伸長、アドテクノロジーの進化で、「動画広告」という広告形式はどんどん規模を拡大しています。そんな中で筆者は、動画広告のリーチや効率の視点については議論されているが、態度変容の差異についてはあまり議論をされていないという印象を持っていました。
思えば4マスの時代、「新聞、雑誌、ラジオ、テレビ」の役割の違いと、そこに適合する広告表現については、クライアントと広告会社の間で一定のコンセンサスがありました。それは経験と勘によるものだったかもしれませんが、結構役に立っていたと記憶しています。
本論は、調査と統計分析を用いて、動画広告でも同じことができないか?というトライアルの結果です。
ストラテジックプランナー、クリエーティブ、メディアプランナー、営業…動画広告をソリューションとして考えている“動画広告料理人”たちが何かを考えるきっかけとなれば幸いです。
「動画広告メディアにおけるCMタイプと態度変容」調査概要
●調査エリア:全国
●調査手法:ウェブ調査
●調査時期:2016年10月
●対象者性年齢:15歳(高校生以上)~59歳男女
●対象者条件:本調査で対象とするメディアのうち「7個」以上を「週1回くらい」以上利用していること
●サンプル数:2301(ワンパターン回答者を除外)
【問い合わせ先】
電通 メディアイノベーション研究部
infomedia@dentsu.co.jp